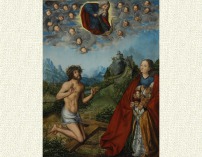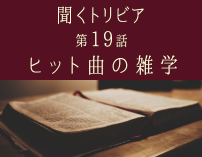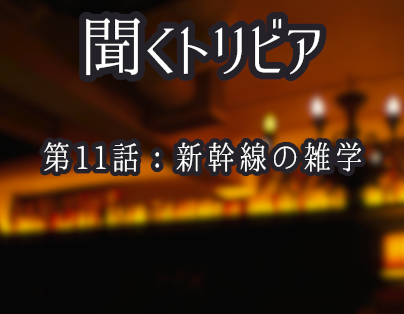運命の三女神の「海の妖精の眷族」イメージはいつ頃から?

キリスト教時代に入って制作されたギリシャ神話を題材とする美術作品では、元ネタの古代神話よりも(いささか無理矢理であっても)大幅に勧善懲悪を感じさせる描写が多く、時には勧善懲悪的なエピソードをわざわざ創作してまで勧善懲悪要素と結び付けられていたわけですが、19世紀半ば〜後半以降になると市民社会の発展などを背景とする社会的文化的な価値観の変化のため、そうした神話画も勧善懲悪要素から次第に自由になってきます。
そうした流れの中で、以前取り上げた人間の運命を司る女神の三姉妹「運命の三女神」像の表現も実は大きく変わっています。
前近代の作品では、この運命の三女神は「人間の運命の不確かさ」をテーマにした余り勧善懲悪的でない作品では年取った女性の姿に、より勧善懲悪的な場合=信賞必罰的で公正なイメージを強調するため「高位の神の部下」として任務に当たる姿が強調される場合には若い女性の姿に描かれることが多かったのですが、19世紀も終わり近くなると、「先のわからない人間の運命の残酷さ」を強調した勧善懲悪的でない作品でも、若々しい美女タイプの運命の三女神が当たり前のように描かれるようになります。
そうした最早「高位の神の部下」ではない、「先のわからない人間の運命の残酷さ」の象徴としての運命の三女神が若い(更にいうと、より妖艶な美女タイプの)外見年齢に描かれるようになった大きな背景には、いわゆるヨーロッパ世紀末芸術の流れの中で、「男性を翻弄ししばしば破滅させる『運命の女(フランス語で「ファム・ファタール」)』 」という女性像が美術や文学、音楽(オペラ)などのヒロインとして人気を博したことが挙げられます。
そうした「運命の女」イメージの妖艶な運命の三女神像を描いた画家は複数いますが、中でも20世紀初頭〜後半に活躍したフランスの画家ギュスターブ・アドルフ・モッサの手になる『運命の三女神』像は頭に鳥の形の飾りを付けている点で異色です。実はこれは、モッサが得意としたギリシャ神話の海の妖精セイレン(フランス語発音ではシレーヌ、英語発音ではサイレン(警報音などの「サイレン」の語源です))にイメージを重ね合わせた表現です。
なお長くなるので今回は詳しい説明は割愛しますが、このセイレンは海の妖精とはいってもより「怪物」的な役回りのキャラクターであり、美しい歌声で船乗りを惑わせて海難事故を起こし犠牲者を食い殺す存在だとされ、人間の女性の顔の鳥であるとされています(なお、セイレンは後にヨーロッパ北部の神話や伝説に登場する上半身が人間で下半身が魚の「水の怪物」と混淆し、様々な伝説や童話に登場する人魚となります)。
そこでクイズですが、この「運命の三女神を一種の“セイレンの眷族”としてイメージする」発想はいつの時代からあるでしょうか?
1,古代ギリシャの、ソクラテスやプラトンが活躍した時代。
2,ルネサンス時代。
3,20世紀初頭。つまりモッサのアイデアが初めて。
・・・正解は、何と1の「古代ギリシャ」です。とはいえ、正確にいうといわゆる「神話」ではなく、若干新しい時代に書かれた「寓話(教訓的な色合いのある例え話)」での描写です。
古代ギリシャで活躍した哲学者の一人プラトンによる『国家』にその寓話は書かれており、そこでは運命の三女神は白い衣装に花冠を被ったいでたちであり、セイレンたちと一緒に過去・現在・未来のことを歌っています。
つまり『国家』では運命の三女神はセイレン同様歌の名手として描かれ、更にはセイレンも運命の三女神も一種の人智を超えた知識の象徴として描かれてもいるわけです。そうした文学的背景もあり、ルネサンス以降には紋章や標章などで(セイレンの派生キャラである)人魚がしばしばポジティブな意味合いで描写されるようになります(スターバックスのロゴもその一つです)。なおセイレンが人智を超えた知識の象徴とされる背景には、彼女らを冥界の王ハデスの神託の伝え手とする神話がありそちらも興味深いものですが、今回は長くなるので深入りしません。
そういえばモッサの描く運命の三女神は、彼女らのアトリビュート(日本語で「持物(じぶつ)」とよばれる、神話や聖書その他有名な物語の登場人物を描く際、それが誰であるかを示すためにほとんど常に一緒に描かれる品物や動植物など)である糸紡ぎ道具やハサミを持つだけでなく楽譜の書かれた本を開いており、「運命の女」としてのセイレン像だけでなく「音楽」と「知識」の担い手としてのセイレン像も投影されていることがわかります。
<参考文献>
千足伸行『隠れ名画の散歩道』論創社、2013
尾形希和子『教会の怪物たち ロマネスクの図像学』講談社選書メチエ、2013
オード・ゴエミンヌ、ダコスタ吉村花子訳、松村一男監修『世界一よくわかる! ギリシャ神話キャラクター事典』グラフィック社、2020
海野弘解説・監修『366日物語のある絵画』パイ インターナショナル、2021
| ジャンル | 歴史 |
|---|---|
| 掲載日時 | 2021/6/26 16:30 |
クイズに関するニュースやコラムの他、
クイズ「十種競技」を毎日配信しています。
クイズ好きの方はTwitterでフォローをお願いします。
Follow @quizbang_qbik
![[PR]簡単!クイズイベントのお助けツールは、アンサータッチ](https://www.quizbang.net/wordpress/wp-content/uploads/2023/06/c442ab583ef5a93b6e362839cfeb0e34-e1685582257127.jpg)