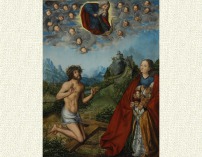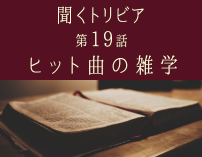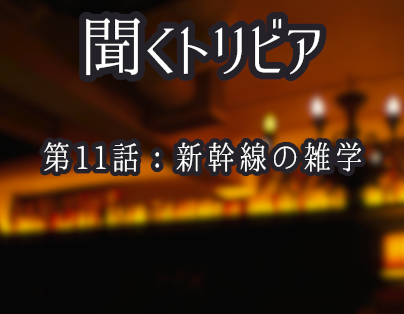平安時代の人にとっての夢ってどんなもの?
現代でも夢はまだまだ謎が多いそうですが「自分の記憶や経験に影響される」というのが通説のようです。
例えばスパイ映画を見た日の夜に、自分もスパイになった夢を見たとか、Aくんのことが好きだから意識しすぎて夢に出てきた、というような具合です。
しかし、平安時代は夢をお告げだと考えていました。ですので、さっきの例と同じように意中のAくんが夢に出てきたら、「Aくんが私のことを恋しく思っているから夢に出てきてくれたんだ!」と考えます。
そして、昔は夢占いを専門とする「夢解き」という職業もありました。
夢解きについては、『宇治拾遺物語』に収められている「夢買う人の事」という話でよくわかります。
あらすじはこうです。
男Aが夢を見たので、夢解きの女のところで夢占いをしてもらう
同じように別の男Bも女に夢解きをしてもらいに来る
男Aは女と男Bが話している様子を隣の部屋から覗いている
男Bの夢は高い地位に上り詰めるとてもいい夢だったという結果をもらい、帰る
男Aが夢解きの女に「男Bの夢を譲ってほしい」と相談する
「では、先ほどの男Bと同じ振る舞いで、同じ言葉で私に向かって夢の内容を語ってください」と女。
男Aは言われた通りに、男Bと同じ行動・同じ夢の内容を語る
男Aは本当にえらくなり、男Bは地位もないまま死んでしまった
【教訓】夢の内容を人に聞かせてはならない
今回の男Bの場合、自分ではどうしようもない気もしますが、夢を人からもらえると考えていたとは驚きです。当時の人の夢に対する扱いが分かるエピソードでした。
またこの教訓を実践できずうっかり人に言ってしまったからこそ失敗した人もいます。
同じく『宇治拾遺物語』に収録されている「伴大納言の事」を見てみましょう。
ある日伴大納言善男という人が西大寺と東大寺をまたいで立った夢を見た
妻に言うと「股が裂けるということなんじゃない?」としょーもないことを言われる
「これはとても高い地位に昇るというお告げの夢でした。それなのにつまらない解釈をされてしまったせいで、高位に昇っても事件が起きて罪を受けることになりましょう」と占い師
本当に大納言という高い地位を得たのに、放火の疑いで都を追放されてしまうことになる

この話では、お告げである夢の解釈を間違ってしまったことで問題が起こってしまいました。一回口に出してしまった言葉は元に戻せないと考えている「言霊信仰」も平安時代の人の考え方っぽいですね。
地動説や、地震・皆既日食のメカニズムなど、今では当たり前のことでも、当時は不可解極まりない現象でした。人間はルールがないことを嫌います。
そこでなんとか説明をつけようとしたのが、夢だったり、お告げだったり、なのです。
当時の人の考え方を知るために「オカルト」現象の解釈を考えるのもおもしろいかもしれませんね。
| ジャンル | 歴史 |
|---|---|
| 掲載日時 | 2020/11/21 16:00 |
| タグ | 宇治拾遺物語 平安時代 |
大阪府出身・在住。
同志社大学文学部国文学科卒業。
現在は予備校で(比較的)新人講師として勤務。
担当ジャンルは【古典文学】
授業では、本編よりも脱線話の方がウケて悲しい反面、過去の自分もそうだったので生徒を責められません。小ネタを収集する日々です。
基本どんなジャンルでも興味あり!
でも、結局言葉(=ことのは)のもつ魅力から逃れられずここまで来てしまいました。
尊敬する人は中2のときからロザンの宇治原さん。好きなことは、得意ジャンルが全く違う同居人とクイズ番組を見ながらやいやい言うこと。
クイズに関するニュースやコラムの他、
クイズ「十種競技」を毎日配信しています。
クイズ好きの方はTwitterでフォローをお願いします。
Follow @quizbang_qbik
![[PR]簡単!クイズイベントのお助けツールは、アンサータッチ](https://www.quizbang.net/wordpress/wp-content/uploads/2023/06/c442ab583ef5a93b6e362839cfeb0e34-e1685582257127.jpg)