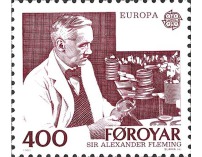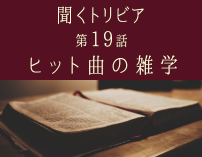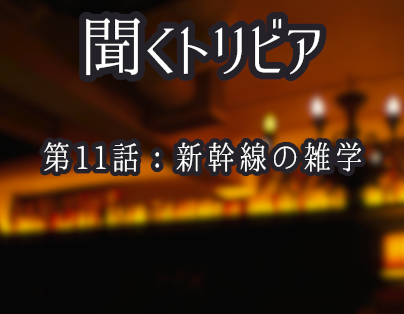2017年に初めて地球上で観測された恒星間天体は?
 恒星間天体ということばを初めて聞いた方は多いだろう。もし知っていれば、天文学に興味を持っており精通していると自負してもいい。
恒星間天体ということばを初めて聞いた方は多いだろう。もし知っていれば、天文学に興味を持っており精通していると自負してもいい。
恒星間天体とは、銀河中に存在する恒星の重力にほとんど影響されることなく移動している天体である。ただしこの天体は彗星・小惑星・惑星などを指しており、恒星や銀河中にもっとも多く存在する星間物質(ガス)を除く。
恒星間天体について定義されたのは2017年に初めて観測されたことがきっかけとなっているため、まだ詳細は分かっていない。
2020年6月現在、太陽系を通過した恒星間天体が観測されたのは2つのみだ。1つは2017年10月に発見されたオウムアムア、もう一つは2019年8月に発見されたポリゾフ彗星である。
まずオウムアムアについて説明しよう。オウムアムアはアメリカのハワイ州、マウイ島にあるハレアカラ観測所で初めて観測された。その名前は「遠方から来た初めての使者」を意味するハワイ語 “ ‘oumuamua”に由来している。可視光線の観測によると、細長い棒状あるいは葉巻状の形をしており、また回転しながら進んでいると推察される。
観測されて以降、「どの銀河系からきたのか」「その天体の正体は何か」などの研究がなされており、2019年にハワイ大学などの研究チームが「オウムアムアは完全なる天然起源の天体である」と発表した。現在も関連研究は進行中である。
2019年に観測されたポリゾフ彗星は、初めて地球上で観測された恒星間彗星である。彗星の名前は発見者のゲナディ・ポリゾフ(クリミア出身のアマチュア天文学者)に由来し、彼はクリミア半島の施設で自作の65cm望遠鏡を用いて観測し発見した。その後の観測から、天体は双曲線的な軌道を持つことが確実視されてIAUから史上2番目の恒星間天体と認定された。ポリゾフ彗星の研究も現在進行中である。
前述したように恒星間天体の観測は始まったばかりで、その数も少ない。またその速度が他の天体と比べて非常に速いため、宇宙からの接近探査では困難なのだ。性質を詳しく知るには、広域を高速かつ高頻度で観測できるモニターを備えたカメラを搭載すれば可能らしい。
| ジャンル | 科学 |
|---|---|
| 掲載日時 | 2020/7/19 16:00 |
クイズに関するニュースやコラムの他、
クイズ「十種競技」を毎日配信しています。
クイズ好きの方はTwitterでフォローをお願いします。
Follow @quizbang_qbik
![[PR]簡単!クイズイベントのお助けツールは、アンサータッチ](https://www.quizbang.net/wordpress/wp-content/uploads/2023/06/c442ab583ef5a93b6e362839cfeb0e34-e1685582257127.jpg)