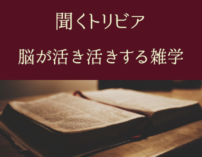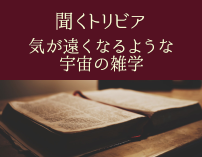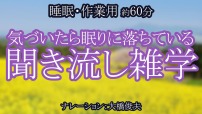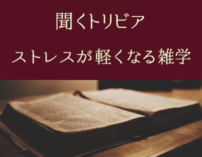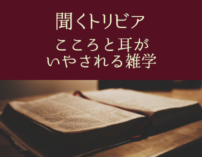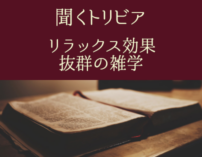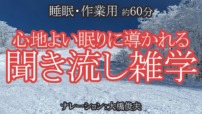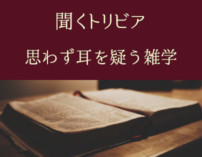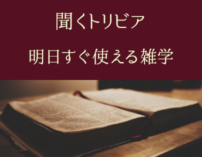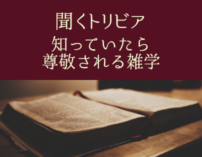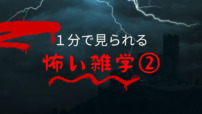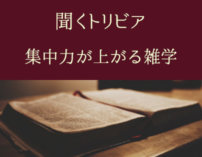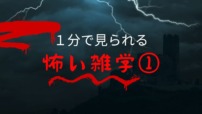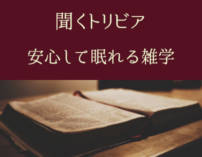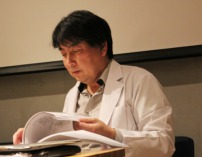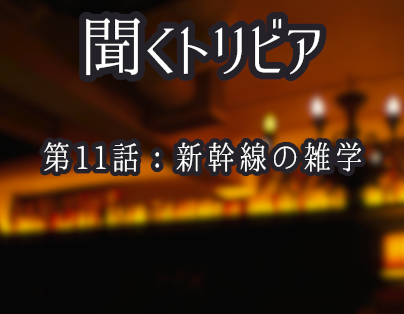『YouTube公開』昭和61年の10円玉は○○万円の価値がある!?
【朗読】眠りながら賢くなれる雑学【聞くトリビア】
『バナナは果物ではない!?』
『20年前、1日の時間が少し短くなった!?』
寝る前に聞くと寝ながら賢くなれる、面白雑学動画!
驚きの雑学の数々を、フリーアナウンサー大橋俊夫氏の朗読とともにお楽しみください。
こちらは動画の内容の書き起こし記事です。
音声と一緒にお楽しみください。
人間の祖先は、鼻の穴が4つあった魚には鼻の穴がいくつあるかご存知でしょうか?正解は4つです。その4つの穴を利用して、魚はうまく水を出し入れし、周囲の匂いをかぎわけているそうです。実は、はるか昔に暮らしていた人間の祖先も、魚と同じ鼻の穴が4つあったそうです。 というのも、人間の祖先もかつて海の中で暮らしていたからです。そもそも、現在地球上で暮らす生命は、すべて海の中で生まれて進化したものです。すなわち、人間も海の中で生まれた生命が進化して現在の姿になったわけです。海の中で暮らしていたということを考えると、魚と同じ特徴を持つのもおかしくないということになります。 実は、現在の人間にも鼻の穴が4つあった頃の名残が残っています。目頭の中に目と鼻がつながっていて、まるで通り道のような部分があります。これがかつて存在した鼻の穴だった部分だそうです。ちなみに、涙を流しているときに同時に鼻水が出ることはないでしょうか。それはこの穴で目と鼻がつながっていることが原因とされています。 |
オーストラリアの原住民は、おやつにアリを食べるオーストラリアの先住民族であるアボリジニ。彼らは現在も、昔からの文化を引き継ぎながら暮らしています。そんな彼らの食生活も独特で、なんとおやつ代わりにアリを食べる習慣があります。 そのアリとは「ミツツボアリ」というアリで、その姿は他のアリと違い、お尻の部分が膨らんでいて透明な飴色をしています。実はこの飴色は、体に溜め込んだ蜜の色で、お尻をタンクにして蜜を保存しているのです。アボリジニはこのタンク部分を噛み潰すようにして食べるそうです。タンク部分は蜜が詰まっているだけあって、その味は非常に甘く、まるでメープルシロップのような味がするそうです。ただ、中には飴色ではなく白色のミツツボアリがいるそうで、それは酸っぱくて、とても食べられるものではないそうです。 なぜミツツボアリはこのような形で蜜を体に溜め込むかというと、彼らはエサが少ない砂漠の中で生きているため、このように蜜を溜め込まないとすぐに死んでしまうからです。また、ミツツボアリには蜜を溜め込まずにエサを運んでくるグループもいます。そのグループのアリに対して蜜を供給する役割もあるのだそうです。 |
フランスでは、かつて1日10時間だった1793年、フランス革命によって新しく誕生した政府は、カトリック色の強いそれまでの暦を廃止し、新たな「革命暦」と呼ばれる暦を制定しました。しかし、この暦は、非常にとんでもないものだったようです。 というのも、1週間を10日、1日を10時間、1時間を100分、1分を100秒といったように、すべて十進法を使って換算されていました。なぜこのような形にしたかというと、通常の暦や時間では60進法を使っていますが、普通の数のように十進法を使えば合理的に進めることができるのではないか、という考えがあってのことだそうです。しかし、今までの生活習慣と大きく異なるため、国民にとっては非常に不評でした。そのため、ナポレオンが皇帝となってから2年後の1806年、革命暦は廃止され、元の暦に戻りました。 ちなみに、革命暦では1年12ヶ月のそれぞれの月の名前は独特で、1月、2月とは言わず、葡萄、霧、霜、雪、雨、風、芽、花、草、収穫、熱、果実とちょっとおしゃれに呼ばれていたようです。 |
生後7ヶ月で即位した天皇がいる現在の今上天皇が即位したのは、59歳の時でした。これは770年に即位した光仁天皇の60歳に次ぐ歴代2位の高齢記録だそうです。では、逆に最年少の即位記録は誰で、何歳だったのかというと、平安時代の終わりに、なんとわずか生後7ヶ月で即位した天皇がいました。 その天皇とは第79代の六条天皇です。六条天皇は二条天皇の子どもとして1164年に生まれました。しかし、翌年に二条天皇は病気が重くなり、誰かに後を継いでもらいたいと考えるようになりました。そこでわずか生後7ヶ月だった六条天皇に位を譲ったというわけです。 しかし、後に二条天皇が亡くなると、一時期力を失っていた後白河上皇が、自分の子どもである憲仁(のりひと)親王を皇太子にして院政を復活させ、六条天皇を上皇へ退位させました。そのため、六条天皇の在位期間はわずか3年ほどでした。 退位後の六条上皇は、後に病気にかかってしまい、13歳の若さで亡くなってしまいます。まだ幼い子どもながら、時代に振り回されてしまったと考えると、非常にかわいそうな話ではあります。 |
昭和61年の10円玉には、平等院鳳凰堂のデザインが違うものがある変わった10円玉と聞いて、皆さんはどんなものを想像するでしょうか。多くの人は、縁の部分に溝が彫られてギザギザになった、いわゆる「ギザ十」を思い浮かべるのではないでしょうか。実は他にも変わった10円玉が存在します。 その10円玉とは、1986年(昭和61年)の後期に発行されたものです。この時期に発行されたものは、実はよく見ると平等院鳳凰堂のデザインが少し変わっています。では、どのような違いがあるかというと、鳳凰堂の屋根の端の形が本来は鈍角なものが鋭角になっているというものです。そして、入口の中央階段の縁が、本来は縦線で分離されているのが、ひとつなぎになっているという非常に細かい違いです。しかし、その違いがプレミア感を呼び、2024年に行われたオークションで、手数料込みでなんと1枚97万円の値がついたそうです。 もし時間があれば、家にある10円玉を調べてみてはいかがでしょうか。保存状態にもよるかもしれませんが、もし昭和61年後期製造のものが見つかれば、数万倍の価値に化けるかもしれません。 |
ギンオビイカが吐く墨は、光る日本近海の水深およそ200mあたりの深海に、体長4cmほどのギンオビイカという小型のイカが生息しています。このイカは、非常に体が小さいのも特徴ですが、もっと驚くべきポイントがあります。それが、吐く墨が光るというものです。 ギンオビイカは深海で暮らしています。深海といえば、光がほとんど届かない世界。どんな生き物でも暗闇で視界が広がらない中で生きています。そんな中、突然の光を受けた生き物は、そのまぶしさに目がやられてしまいます。ギンオビイカはその状況を利用して、光る墨を吐いているのです。光る墨を見た敵は目がくらんでひるんでしまうか、驚いて逃げてしまいます。そうすることで自分の身を守っているのです。 しかし、実際にはこの墨自体が光るというわけではないそうです。ギンオビイカが墨と同時に青白く光る液体を出すことで、墨自体が光って見えるというわけです。また、光るとは言ってもそれほど強い光ではなく、地上でその墨を見てもあまり光って見えないぐらい弱いものだそうです。真っ暗闇の深海だからこそ、弱い光でも十分効果があるのでしょう。 |
鉄より硬いプラスチックがある鉄とプラスチック、どちらが硬いか。そう聞かれるとほとんどの人は「鉄」と答えるのではないでしょうか。しかし現在、その常識を覆す新たなプラスチックが存在します。 これは2010年に広島大学の研究チームが開発したもので、プラスチックの中でももっとも軽い素材であるポリプロピレンの製法を改良して生み出されました。この素材は鉄に比べて2~5倍の強度を持ち、耐熱性も通常のプラスチックより高く、それでいて通常のプラスチックと同じコストで作ることができ、再生可能であるという非常に優れた特徴を持っています。 現在、このプラスチックは多くの製品に取り入れられています。その代表例として自動車や船などの乗り物があります。鉄と比べて軽いため、動かすための燃料が少なく済むというメリットがあり、また船の場合は長い間海水に浸かっても錆びることがないということから、多くのメーカーが取り入れているとのことです。 今まで鉄で出来ていたものすべてが、すべてプラスチック製になる日も、そう遠くないかもしれません。 |
胴上げはもともと、お祓い目的で行われていたよくプロ野球の優勝チームが行う胴上げ。お祝い事で行われることがほとんどですが、実はこの胴上げ、もともとはお祓い目的で行われたのが最初だそうです。 胴上げの風習が始まったのは江戸時代で、節分の日に江戸城などのお城で豆まきをするときに、豆をまく人に対して胴上げを行っていたのが最初とされています。当時、豆まきという役目は鬼と対決しなければならない、いわば「汚れ役」であると考えられていました。そのため、その年が厄年である男性が選ばれていたそうです。そんな汚れ役をする人の厄災を少しでも祓ってあげようと、その人物を高く投げ上げ、体にまとわりついていた厄災を取り除こうとしたそうです。これが胴上げの元祖だといわれています。 このような由来があるため、当然、胴上げは日本独自の文化です。海外ではこの習慣がないため、プロ野球の助っ人外国人は優勝時に胴上げが行われている際、意味がわからなかったそうです。ただ、21世紀に入ってからは海外でも胴上げをしている姿が見られるようになりました。一説によると、多くの日本人選手が海外のプロスポーツリーグに参加したことがきっかけで伝わったのではないかと言われています。 |
野球はかつて、「打球鬼ごっこ」と呼ばれていた野球、ベースボールが日本に伝わったのは明治の初頭のことでした。当時はまだ「ベースボール」の訳語として「野球」という言葉は生まれていませんでした。では何と呼ばれていたかというと、なんと「打球鬼ごっこ」だったそうです。 これは1885年(明治18年)に刊行された『西洋戸外遊戯法』という本に書かれていた名称で、この本には「打球鬼ごっこ」としてそのルールが掲載されていたようです。また、小学生用の指導書にも詳しく書かれており、そこには「打球鬼ごっこ」を略した「打球鬼」という名前で呼ばれていたことが記されています。 「野球」という言葉が生まれたのは1894年(明治27年)のことで、当時、第一高等中学校のベースボール部に所属していた中馬庚(ちゅうまん・かのえ)という人物によるものです。彼は練習の合間にルールの解説や翻訳などに取り組み、その一環として「野球」という言葉を生み出したそうです。ちなみに、彼は後に日本初の野球専門書を書き、その業績から1970年に野球殿堂入りを果たしています。 |
「のたうち回る」という言葉は、イノシシの様子から生まれた「あまりの痛みにのたうちまわる」といったときの「のたうちまわる」。苦しみや痛みでもがいて転げ回るという意味がありますが、この言葉は実は、イノシシのある様子から生まれました。 「のたうちまわる」の「のた」とは、もともと「ぬた」といい、沼地などを表す言葉でした。イノシシはその沼の中で泥にまみれて寝転がることがあるそうです。こうすることで体の熱を冷ましたり、虫に刺されるのを防いでいるそうです。その様子が「ぬたうつ」と呼ばれるようになり、それがなまって「のたうつ」と変化しました。 その後、人が家などで横になってゴロゴロしている様子も「のたうつ」と言われるようになり、さらにそこに苦しみや痛みの要素も加わるようになって、現在の「のたうつ」「のたうちまわる」という意味の言葉に変化していったということです。 |
テニス、ウィンブルドン大会のパトロールには、鳥のタカも参加しているテニス界を代表する大会、ウィンブルドン。多くのスタッフが大会の成功に向けて尽力していますが、中には変わったスタッフも存在します。それが鳥のタカであるルーファスです。 ルーファスはどのような仕事をしているかというとハトの撃退。試合中にハトが飛んできて試合を邪魔し、中断することも多々あるそうです。そんなときにルーファスが追い払い、試合をスムーズに進行させているというわけです。現在はルーファスだけでなく、ポラックスという名前の若い後輩タカも空のパトロールに参加しています。最近は屋根つきのコートで試合が行われることが多く、ハトが止まる場所が増えることから、彼らの仕事は以前よりも増えているとのこと。 そんなルーファスは、ウィンブルドン以外にも、ロンドンのウェストミンスター寺院をはじめ、サッカーやラグビーの試合でも活躍しています。多くのイギリス国民に愛されているルーファス。いつまでもがんばってほしいものですね。 |
2004年のスマトラ沖地震の影響で、1日の時間が短くなっている2004年12月26日、インドネシアのスマトラ島沖で、マグニチュード9.0と推定される巨大な地震が発生しました。インドネシアのみならず、タイやマレーシアといったアジアの国々に津波が到達し、死者・行方不明者が30万人以上にのぼるという甚大な被害を出しました。実はこの地震、そのような被害とは別に、ある興味深い現象を引き起こしていました。それが、1日の時間が短くなったというものです。 スマトラ沖地震はアジアの周辺だけでなく、地球全体の形状にも影響を与えました。地球がどれほど球に近いか、または平べったいかを示す「扁平率」という値がありますが、この地震の影響で扁平率が100億分の1ほど減少しました。この変化は地球の自転速度にも影響を及ぼし、地球の自転がおよそ2.68マイクロ秒ほど速くなったことも判明しました。1マイクロ秒とは、1秒の100万分の1です。その結果、1日の時間が1日あたり100万分の2.68秒ほど短くなったそうです。 とはいえ、この時間の変化は非常にわずかであり、人間が日常生活の中で気づくレベルの話ではありません。また、このような微細な変化は、うるう秒やうるう年などの調整によって補正されるため、我々の生活に特に影響を与えることはありません。 |
かつて横断歩道は、チェック柄だった現在見られる横断歩道の多くは縞模様となっています。かつてはその縞の両端にも白い線が引かれており、はしごのような形をしていました。では、このはしご型以前の横断歩道の形を知っている人はどれだけいるでしょうか。実は1960年頃の横断歩道はチェック模様をしていたのです。 このチェック模様とは、はしご型の横断歩道を左右で2つに分解し、それぞれの白線部分をずらしたようなデザインで、現在のものよりも派手な見た目をしていました。しかし、当時は車の交通量が現在よりも多く、交通事故による死者数は増加の一方をたどりました。そこで1965年にはデザインを簡略化して、設置作業の効率化を図ることで、横断歩道のさらなる増設を目指しました。この際に誕生したのが、はしご型のデザインです。 さらに1992年には、現在の横断歩道のほとんどで採用されている、はしご型から両端が省略された形状のデザインになりました。ちなみに、はしご型から両端の白い線が無くなった理由は、塗装コストの軽減と、雨水がたまりにくくなるというメリットがあるためです。 |
渋谷には「間坂(まさか)」という坂がある東京都渋谷区の宇田川町の井の頭通りから公園通りへと抜けるところにある、渋谷Loft沿いの坂には非常に変わった名前がつけられています。その名も「間坂(まさか)」。何も知らずに聞くと、ふざけた名前のようにも思えるこの坂は、実際に地図にも掲載されている正式な名前の坂です。 この名前は、1989年に渋谷Loftがオープンする際に行われた一般公募によって命名されました。「渋谷駅と公園通りとの間にある」「ビルとビルの間にある」「『間』という漢字が人と人との関わり合いをイメージさせる」などの理由から、この名前が選ばれたそうです。 ちなみに、Loftの店舗の端には坂の名前が彫られた石碑が建てられています。命名されたのは1989年(平成元年)ですが、この石碑は昭和63年に建てられたと記されています。なぜ、1年のずれがあるのか、その原因ははっきりとわかっていません。 |
太平洋戦争中、ラジオで天気予報は放送されなかった日本で初めて天気予報が出されたのは1884年(明治17年)のことでした。当時はテレビはもちろん、ラジオ放送もなかったため、天気予報は交番の前に貼り出す形で伝えられていました。そして大正時代に入り、ラジオ放送も始まり、天気予報はラジオを通じて伝えられるようになりました。その後、天気予報は毎日のように放送されていましたが、実は太平洋戦争中にはラジオで天気予報の話題は一切取り上げられなくなりました。 というのも、天気の情報は戦争の行方を左右する重要な機密事項とされていたからです。たとえば、爆撃機が日本を襲う際には、晴れていたほうが見通しが良く、攻撃がしやすくなります。そのような情報が敵国に知られてしまうと、日本は一気に攻撃を受けてしまう危険性があります。そのため、ラジオでは天気予報が流されず、気象台などの観測データはすべて暗号化され、各組織へと伝えられていました。 戦争が終わり、ラジオからは再び天気予報が流されるようになりました。天気予報が当たり前のように確認できる今の状況は、ある意味、平和であることの証明なのかもしれません。 |
戦国時代、饅頭屋さんが作った国語辞典があった戦国時代の林宗二(りん・そうじ)という人物は、当時の印刷技術を使って日本最初の辞典を作ったとされていますが、驚くべきことに、彼は饅頭屋として働きながらこの辞典を編纂したそうです。 もともと彼は京都の饅頭屋の家に生まれ、後に奈良へと渡り、戦国大名・松永久秀の後援を受けて奈良一帯で饅頭を独占的に販売するなど、商売人として成功をおさめていました。しかし、彼はそれだけでなく、商売のかたわら様々な学問を学び、その分野でも才能を発揮しました。たとえば『源氏物語』の注釈書である『源氏物語林逸抄』や、漢詩『長恨歌(ちょうごんか)』を書き写した抄写『長恨歌抄』などの書物を残しています。そして、その一環として日本史に名を刻む日本最初期の国語辞典『饅頭屋本節用集(まんじゅうやぼんせつようしゅう)』を編纂したのでした。 この辞書は当時ベストセラーとなり、江戸時代にも再販されるほどの人気を誇りました。戯作者・山東京伝はこの辞書を参考にして作品を執筆したとも言われています。 |
柑橘類のかぼすは、蚊を追い払うために使われていた大分県特産の柑橘類、かぼす。ポン酢や酢の物、焼き魚などに使われ、脇役として料理を大いに引き立ててくれます。そんなかぼすですが、もともとは食べるものではなく、別の目的で利用されていたそうです。 かぼすはもともとヒマラヤ地方原産で、江戸時代に中国から日本にやってきました。当初は薬として食べられていましたが、その皮は蚊を追い払うのに利用されていたそうです。かぼすの皮には蚊が嫌がる成分があるらしく、当時は皮を刻んで蚊取り線香代わりに使っていたという記録が残っています。 実は「かぼす」という名前の由来は、この皮が虫を追い払う役割に関係しています。虫などを追いやることを「いぶす」と言い、蚊などを皮を使って“いぶして”いたことから、「蚊をいぶす」がなまって「蚊いぶし」、「蚊ぶし」となり、最終的に「かぼす」という名前になったそうです。 ちなみに、現在、日本で生産されるかぼすのおよそ95%は大分県で生産されています。大分では古くから現在の竹田市や臼杵市の民家の庭で栽培されており、それが大分県内に広がり、生産が盛んになりました。臼杵市には樹齢300年を超えるかぼすの木も現存しているそうです。 |
神社で行う神前結婚式を最初に行ったのは、大正天皇神社などの神殿で行われる神前結婚式。そのスタイルから、かなり昔から行われているものと思いがちですが、実はその歴史はそれほど古くありません。 最初に神前結婚式という形で行われたのは1900年(明治33年)、当時の皇太子である大正天皇の結婚の儀でした。正装した男女が皇居の神殿で結婚の儀を行ったことは、国民の間で大きな話題となりました。そして、大正天皇にあやかりたいという声が高まり、東京大神宮が民間向けに神前結婚式のスタイルを定め、翌年の1901年(明治34年)からサービスを開始しました。これにより、多くの人が結婚式を挙げるようになり、この形式が定着したそうです。 では、それまではどのようにして結婚式が行われたかというと、新郎側の家に身内だけが集まり、そこに祀られている神様の前で結婚式を行うという、こぢんまりとしたスタイルがふつうでした。 ちなみに、ホテルなどの結婚式場で神前結婚式を行えるところもありますが、そのきっかけは関東大震災が起こったときに、多くの神社が被害を受けたため、ホテルの宴会場の一角に祭壇を設けたことがきっかけだとされています。 |
草津温泉という名前は、臭いことから名付けられた群馬県の名湯・草津温泉。毎年多くの観光客が訪れ、その湯を楽しんでいます。そんな草津温泉の「草津」という名前の由来には、実はその温泉の匂いが大きく関わっています。 草津温泉のお湯は硫黄成分が強く、独特の匂いが特徴的です。そのことから、当初この地は「臭い水」という意味の「臭水(くそうず)」と呼ばれるようになりました。次第にその言葉がなまっていき、やがて「草津」と呼ばれるようになったそうです。ちなみに草津の人はその名残から、「くさつ」とは読まず、「くさづ」と「つ」に濁点をつけて読んでいます。 しかし、「臭い」というネガティブなイメージを地名につけるのは奇妙に思えるかもしれませんが、かつてこの温泉の強烈な匂いが邪気を払うと考えられていたため、特に違和感なく命名されたようです。 |
車の暖房は、ガソリンを消費しない冬の寒い日に自動車を運転するとき、暖房は欠かせません。しかし、暖房を使うと燃費に影響するのではないかと考えて、使うのを控える人もいるかもしれませんが、実はその心配は不要です。暖房の使用にガソリンなどの燃料は直接関係ありません。 というのも、車の暖房はエンジンをかけることによって発生した熱を利用しているからです。エンジンを動かすと大量の熱が発生するため、冷却水で温度を下げる必要があります。その際の温められた冷却水に風を当てることで発生した暖かい風が車内に送られ、車内が暖まる仕組みになっています。すなわち、暖房を使用しても、燃料を追加で消費するわけではないため、節約しても燃費に影響はありません。冬場は安心して暖房を使いましょう。 ただ、逆に冷房は冷たい空気を作るコンプレッサーを動かす動力が必要で、その分ガソリンなどを消費してしまいます。もし少しでも節約したいと思うなら、車を停めているときに遮光シートを使用するなどして、太陽の熱で車内が熱くならないように工夫するのが効果的です。 |
花瓶に花を活けるとき、サイダーを入れると長持ちする家で花を飾るとき、すぐに枯れてしまうという人も多いのではないでしょうか。その理由は、水の中でバクテリアが発生し、花の切り口に繁殖して水の吸い上げを妨げてしまうからだそうです。では、どうすれば長持ちさせることができるのでしょうか。 実は、水の中にサイダーを入れることで、簡単に長持ちさせることができます。サイダーに含まれる炭酸ガスにはバクテリアの繁殖を抑える効果があり、さらにサイダーの糖分がエネルギー源になることで、花をよりきれいに咲かせることができます。 やり方は簡単で、サイダーの炭酸を少し抜いた状態で、花瓶の水に対して2割ほどの割合で混ぜればよいだけです。ただし、これでも完全にバクテリアの発生を防げるわけではないので、定期的に水を入れ替える必要があります。 サイダーでなくても、無色の炭酸飲料でも代用可能です。できれば、果糖ぶどう糖液糖が含まれる炭酸飲料のほうが、通常の糖よりも粒子が小さく、花に吸収されやすいため、より効果的だそうです。ただし、コーラなどの色がついた炭酸飲料は酸が強く花が痛みやすくなるため、使用する場合は量を減らすなどの工夫が必要です。 |
防犯用のカラーボールは、強盗を狙ってはいけない金融機関やコンビニなどには、強盗の襲撃に対応できるよう、防犯カラーボールというものが設置されています。このボールは、強盗に投げると特殊なインクが体について、捜査に役立つ防犯アイテムですが、その使い方を勘違いしている人が少なくありません。強盗を直接狙うように投げると思いがちですが、実は足元の地面に向けて投げるのが正しい方法です。 というのも、強盗に向かって投げても、的は小さく、しかも動いているため当てることは簡単ではありません。また、たとえ当たっても衝撃が弱く、ボールが割れずにインクがつかないこともあるそうです。 そこで、強盗の足元の地面に向けて投げることで、地面との衝撃でカラーボールが割れて、中のインクが犯人の足につけることができます。それだけで犯人の特定につながるため、直接狙う必要はないのです。 金融機関などで働かない限り、あまり役立つ機会がない知識ではありますが、覚えておけば今後どこかで役に立つ可能性があるかもしれません。頭の片隅にでも入れておくと良いでしょう。 |
ヤブ医者という言葉は、もともと褒め言葉だったヤブ医者と聞けば、技術が未熟で患者に対し適切な診療ができないダメな医者というイメージがあるでしょう。しかし、もともとヤブ医者という言葉はかつては褒め言葉として使われていたことがあります。 ヤブ医者という言葉が生まれたのは江戸時代のことだそうで、当時は医師の資格制度が整っておらず、誰でも医者と名乗ることができ、そのような資格を持たない町医者などをヤブ医者と呼んでいました。資格を持たないということは、満足な治療ができないのではないかと思うかもしれませんが、彼らは患者の話をよく聞き、適切な治療を施したことや、庶民向けに安い値段で診察してくれたことから、厚い信頼を受けていました。。このため、ヤブ医者はむしろ信頼できる医者と考えられていたそうです。 しかし、明治時代になると、医師の資格制度も整備され、資格なしで診察を行うヤブ医者はほとんどいなくなりました。その結果、ヤブ医者という言葉は、資格なしで技術も未熟な医者を指す悪口に変化していきました。 |
上野動物園のラクダが靴を履いていたときがある1882年に博物館の付属施設として開園した上野動物園。今まで多種多様な動物が飼育され、多くの人たちの目を楽しませてきました。その動物のひとつにラクダがいますが、かつてこのラクダが靴を履いていたというエピソードがあります。 とはいっても、おしゃれで靴を履いていたわけではありません。これは1966年のことで、あるラクダが足の皮膚が異常に厚くなる病気にかかり、立っているのもつらい日々を過ごしていました。その状況を見かねたある靴屋さんが、そんなラクダにぜひ靴をプレゼントしたいということで、そのラクダに靴を履かせてあげたそうです。おかげでラクダも痛みがやわらいだとのこと。 その後、ラクダが靴を履き潰すたびに靴屋さんは何度も靴をプレゼントしましたが、残念ながら1973年、そのラクダは結局足の病気が原因で亡くなってしまいます。残念な話ではありますが、きっとこのラクダも靴屋さんの優しさを感じていたことでしょう。 |
バナナは、草である南国で栽培されているバナナ。巨大な木に実として成っているイメージが強いですが、実はあれは木ではなく、巨大な草なのです。 木の幹に見える部分は、実は茎です。実際、外側から葉っぱを1枚ずつはがしていくと、中には何も残らない構造になっています。また、寿命は1年ほどで、一度実をつけるとそのまま枯れてしまいます。そのため、バナナ農家の人は収穫を終えると茎を伐採するという仕事が残っています。 なぜバナナの草があれだけ巨大になったのか、その理由はわかっていません。ただし、巨大化するために多くの水分を補給しているそうです。茎に蓄えている水分量はおよそ50~100リットルほどで、茎の8~9割ほどは水分で構成されているとのこと。それだけの水分が、あれだけ巨大なバナナの草を作り上げているというわけです。 さらに、バナナが草であるということにより面白いことが判明します。農林水産省では、木に成るものは果物、草から穫れるものは野菜と定義しています。すなわち、われわれが果物のつもりで食べていたあのバナナは、実は野菜だったのです。 |
脱獄犯が裁判官になったことがある明治時代、一度捕まって刑務所に服役した犯罪者が、裁判官になったというとんでもない出来事がありました。それは渡邊魁(わたなべ・かい)という人物で、彼はある商社に勤務していた頃に資金を着服し、逮捕され無期懲役の罪に服していました。 しかし、その服役中に脱獄し、潜伏生活を経た後、戸籍を捏造して辻村庫太(つじむら・くらた)という名前で新しい人生をスタートさせました。そしてその後、裁判所の職員として働き、逮捕から10年以上経たった1887年に判事試験に合格し、その3年後にはついに判事に就任するまでに至ったのです。 ところが、一部で辻村判事の顔がかつての脱獄犯・渡邊とそっくりであるという噂が広まり、警察が捜査を開始しました。そして、1891年、出張先の旅館で渡邊はついに捕まり、身柄を拘束されました。一時は否認していたものの、最終的には自白し、再び服役することとなります。 しかし、その時点で着服と脱獄の罪に関してはすでに時効となっていて、戸籍を偽造したという罪についても役所の職員が行ったことであるという理由で無罪となったそうです。その後、出所した渡邊は判事に戻ることなく、地元の長崎で余生を過ごしたということです。 |
カマキリのオスは交尾中に、首を噛み切られるカマキリも子孫繁栄のために交尾を行いますが、そのときのオスほど気の毒な存在はありません。というのも、交尾中にメスに食べられる可能性があるからです。 メスのカマキリはオスより体が大きいため、オスが抵抗しても簡単に力でねじ伏せることができます。メスが空腹であれば、オスはちょうど良いエサになるというわけです。オスも交尾に忙しいため、抵抗する余裕もありません。 ただ、オス側にとっても食べられることでメリットがあります。食べられたオスと交尾したメスは通常の2倍の数の卵を産むそうです。すなわち、それだけ多くの自分の遺伝子を引き継いだ子孫を残すことができるというわけです。 とはいえ、オスも常に食べられるというわけではなく、その確率は25%ほどだそうです。それでも4分の1の確率で命を落とす可能性があることを考えると、そこまでして自分の子孫を残したいオスの必死さに驚かされます。 |
宮本武蔵は、画家としても活躍していた佐々木小次郎との巌流島の決闘でもおなじみの江戸時代の剣豪・宮本武蔵。そんな彼には剣豪からは想像できない別の一面も存在しました。それが日本画家としての顔です。 宮本武蔵は常に闘っていたイメージが強いかもしれませんが、普段は家にこもって絵を描いていたそうです。また、絵画以外にも連歌や書の作品も手掛けており、芸術家としての顔も持っていたことがわかります。 武蔵の絵画作品には水墨画が多くあります。『鵜図(うず)』『枯木鳴鵙図(こぼくめいげきず)』『紅梅鳩図(こうばいはとず)』は特に名作として名高く、これらは国の重要文化財に指定されています。また、同じく武蔵がデザインした刀の鍔も熊本県の文化財に指定されています。それだけ芸術家としての腕も認められていたというわけです。 そんな武蔵の絵画作品は東京都文京区の永青文庫や、大阪の和泉市久保惣記念美術館に所蔵されています。機会があれば見に行ってはいかがでしょうか。 |
孔子の子孫は、全世界に300万人以上いる春秋時代の中国の思想家・孔子。彼の思想は弟子によって『論語』にまとめられ、多くの人に親しまれています。2005年、孔子に関するある驚くべきデータが発表され、話題となりました。 そのデータとは、孔子の子孫が全世界に300万人以上いるということです。うち250万人ほどは中国国内、残り50万人は中国以外の国に住んでおり、特に韓国には10万人ほどいるとされています。 これは、中国の孔子家系図研究センターが発表したもので、このセンターでは、中国などに暮らす「孔」という名字の人々の協力を得て、10年ほどの歳月をかけて調査を行い判明した結果です。 実は孔子の家系図は60年に一度、改定されており、今回の発表はその一環として行われたものです。次回の改定の際には、子孫の人数はもっと増えているかもしれません。 |
遠心力という力は、存在しないよくバケツに水を入れて腕を回転させても水が落ちないのは「遠心力」が働いているからと言われますが、厳密には違います。というのも「遠心力」という力は実際には存在しない概念だからです。 我々が「遠心力」と思っている力の正体は「慣性の法則」でおなじみの「慣性」です。「慣性」とは、他からの力を受けない限り、現在の運動状態を保つ性質のことです。よく電車が急ブレーキをかけたときに立っている人が前に傾く現象で説明されます。電車がブレーキをかけると電車は止まりますが、人間は止まらないため、前に傾きます。つまり、人間の体は前に進もうとする運動状態を保とうとしているわけです。バケツの水も同様で、本来ならバケツの水は底へと向かいますが、バケツを振り回しても外からの力を受けないため、その運動状態を保とうとするのです。すなわち、慣性により水が落ちないというわけです。 この慣性が、バケツを回している人から見ると、あたかも外へ引っ張るような力に感じられるために、その力が「遠心力」という名前で呼ばれているのに過ぎないのです。 |
アリジゴクは、後ろ向きにしか進めないウスバカゲロウの幼虫、アリジゴク。砂の中にすり鉢状の巣の穴を作り、その真ん中でアリが来るのを待ち構える習性がよく知られていますが、そんなアリジゴクは非常に変わった特性を持っています。その特性とは、後ろ向きにしか移動できないというものです。 というのも、アリジゴクは全身に毛が生えていて、これが滑り止めの役割を果たしています。この毛が邪魔で前進することができないのです。巣穴を作るときは、まず外周を作り、そこから内側を後ろ向きに円を描くように進みながら掘っていき、最後に中心の最も深い部分を作ります。巣を作ることに関しては、特に不便な様子はないようです。 ただ、前進できないため、自分からエサを捕まえることは難しいらしく、そのため、あのような罠を作ってじっと待ち続けているわけです。エサがやってこないとどうなってしまうのでしょうか。その点も大丈夫。数ヶ月間何も食べなくても生きることができる生命力の持ち主でもあります。 |
電話が日本に登場した当初、呼びかけの言葉は「もしもし」ではなく「おいおい」だった電話がつながったとき、通常は相手に「もしもし」と呼びかけます。しかし、日本で電話が最初に開通した1890年当時、「もしもし」という言葉は使われておらず、代わりに「おいおい」と言っていました。 「おいおい」という呼びかけは、古くから使われてはいました。当時は高級官僚や実業家しか電話を持っておらず、また電話をつなぐために必要だった電話交換手も男性ばかりだったため、このようなやや威圧的な言葉が用いられていたとされています。ちなみに「おいおい」と言われたら、相手は「はい、ようござんす」と返答していたそうです。 しかし、次第に電話交換手に女性が増えてきたため、「おいおい」という言葉は乱暴に聞こえるという理由で考案されたのが、「申し上げます、申し上げます」と丁寧に繰り返した言葉の略である「もしもし」だったそうです。最初は女性用に考えられた「もしもし」でしたが、後に男性にも浸透していき、一般的な表現となりました。 |
ストッキングはもともと、男性が履くためのものだった現在は多くの女性が着用しているストッキング。その誕生は15世紀頃のヨーロッパだとされています。ただ、驚くべきことに、当時は女性ではなく、男性のファッションアイテムとして愛用されていたそうです。 というのも、当時の貴族の男性は丈の長さが膝あたりまでしかない半ズボンをよく履いていました。そこでヒザ下を隠す形で身に着けていたのが「ホース」と呼ばれる長い靴下でした。これがストッキングの元祖とされています。それに対し、女性はロングドレスを着用することが多かったため、ストッキングを使う必要がなかったそうです。 そして時は過ぎて、フランス革命の時代になると、多くの男性が膝丈の半ズボンから革命派の象徴となる長ズボンを着用するようになり、ストッキングを履く必要がなくなりました。一方で、女性は丈の短いスカートを着用するようになったことから、ストッキングを履くようになりました。 ちなみに、日本では明治時代にはすでに女性の間でストッキングが着用されていたようで、当時の絵画や写真には女性がストッキングを履いている姿が見られます。ただ、具体的にいつ頃日本にやってきたかは、はっきりとはわかっていません。 |
世界一強いお酒のアルコール度数は、96度お酒に含まれているエチルアルコールの度合いのことを「アルコール度数」と言います。この値が高いほど、酔いやすく、より強いお酒であるということになります。普段飲むお酒だと、ビールが4~5度、ワインが13~14度、日本酒が15~17度であり、高いものではブランデーやウイスキーが40度ほどのアルコール度数となっていますが、中にはとんでもない度数のお酒もあります。 それが、ポーランドのウォッカの一種「スピリタス」で、度数はなんと96度にもなります。お酒は製造過程で蒸留を繰り返すことでアルコール度数が高まりますが、このスピリタスはなんと70回以上蒸留されているそうです。それだけ強いお酒であるため、火を近づけるとすぐに引火してしまいます。また、ポーランドでは飲み物としてだけではなく、消毒や感染症の治療にも使われているほどです。 さすがにそれだけ強いお酒であるため、ストレートに飲む人はあまりいないようです。もしストレートで飲んでしまうと、喉が焼けてしばらく声が出せなくなり、場合によっては少量でアルコール中毒になる可能性があります。そのため、ほとんどはジュースなどと混ぜて、カクテルとして楽しまれているそうです。 |
二階建てのエレベーターがあるビルの移動手段として設置されているエレベーター。その中には変わったものもあります。そのひとつが「ダブルデッキエレベーター」というものです。これは上下2つのかごが設けられた、いわゆる「2階建てのエレベーター」です。 1931年にアメリカのオーチス・エレベータ社が開発したもので、上下2つのかごに人を乗せて移動させることができるため、輸送能力を最大2倍近くまで高めることができます。また、1つのエレベーターのスペースで2台分のかごを納めることができるので、建物内に占めるエレベーターのスペースを減らすことができ、その分、オフィスフロアを広くとれるメリットがあります。 ただ、構造上、下のかごは1、3、5階といった奇数階、上のかごは2、4、6階といった偶数階にしか停止できず、利用者が不便に感じるというデメリットもあります。 とはいえ、輸送効率の高さから採用しているビルも多く、六本木ヒルズ森タワーや虎ノ門ヒルズなどの高層ビルにもこのエレベーターが設置されています。興味のある方は利用してみてはいかがでしょうか。 |
ホーホケキョと鳴くウグイスは、オスだけウグイスの「ホーホケキョ」という鳴き声を聞くと、春がやってきたな、と感じずにはいられません。実はこの鳴き声、どのウグイスでも発するものかと思いきや、オスだけなのです。 この「ホーホケキョ」という鳴き声のことを「さえずり」といいます。このさえずりは繁殖期を迎えたオスが自分の縄張りにメスを呼び込むために発するもので、すなわち、パートナーがいないオスしか「ホーホケキョ」と鳴かないというわけです。ウグイスは一夫多妻制で1羽のオスが複数のメスとパートナーになります。そのため、オスの間で非常に激しい争いが行われます。すなわち、オスのウグイスは春先になると必死に鳴き続けるというわけです。たまに夏頃まで「ホーホケキョ」と鳴くオスがいますが、これはパートナーが見つかっていない、いわゆるモテないオスなのです。 また、ウグイスはオスもメスも「チャッチャッ」と舌打ちするように鳴くことがありますが、これは「地鳴き」または「笹鳴き」と呼ばれる鳴き声で、他のウグイスが近づいてきたときに、自分がここにいるということを知らせるために出す音です。 |
シルエットという言葉は、シルエットさんという人物が由来輪郭を描いて中を黒く塗りつぶした絵のことを「シルエット」と呼びますが、この「シルエット」という言葉は、人の名前から来たものだそうです。18世紀フランスで、ルイ15世のもと財務大臣として働いていたエティエンヌ・ド・シルエットという人物がその人です。では、なぜ彼の名前がこのような意味になったのでしょうか。 彼が財務大臣として働いていた時代のフランスは、戦争などの理由で財政困難に陥っており、予算のやりくりに相当苦労していたようです。彼は少しでも節約しなければならないということで、様々な打開策を打ち出すようになり、そのひとつとして、肖像画をちゃんとした絵ではなく影絵にすれば、絵の具の費用を節約できるのではないかと考えました。そして、その後描かれた肖像画はすべて黒で塗りつぶすよう命じました。 しかし、そのような極端な政策が批判を呼んだのか、シルエットは短期間で財務大臣を解任されました。これらの政策に不満を持っていた貴族たちは、シルエットのことを「輪郭だけで実体がない人間」と嘲笑しました。そのことから、皮肉の意味を込めて、輪郭だけの黒い絵のことをシルエットと呼ぶようになったそうです。 |
イギリスには座ると呪われて死ぬ椅子があるイングランドの北部の街、サースク。ここにある博物館には、非常に恐ろしい椅子が展示されています。それは座ると死んでしまうという呪われた椅子です。 この椅子は「バズビーズチェア」というもので、1702年に義理の父親を殺した罪で死刑になったバズビーという男が、生前よく訪れていたパブでいつも座っていた椅子でした。バズビーは相当この椅子が気に入っていたらしく、死刑に処せられたとき、「俺の椅子に座ろうとする奴は、呪われてすぐ死ぬことになる」と叫んだとされています。そして、実際にその椅子に座った人が次々に死んでいったということで話題となりました。これまでに、この椅子に座って命を落とした人は60人を超えるそうです。 さすがに面白半分で座ろうとした人も多かったため、パブ側もさすがにそれはまずいということで、椅子を博物館に寄贈しました。現在は、間違って誰かが座ってしまわないように、壁にかけられた状態で展示されています。 |
入試に双子枠を設けている中学校がある東京大学教育学部附属中等教育学校では、一般入試に双子枠と呼ばれる、非常に変わった受験生の枠が設けられています。 この学校では、双子の知的発達や筋力、運動能力についての類似点や、学力差への影響などを研究・調査しています。そのため、さまざまな実践や調査を通して双子研究を進める目的で、双子の入学を積極的に受け入れているそうです。 ただ、積極的に入学させるとはいえ、推薦ではなく一般入試での受験であるため、ハードルが相当高いことは間違いありません。入学できる双子の数も毎年1~10組と、試験の出来によってばらつきがあるそうです。 当の双子たちにとっては、研究材料のような形での入学のため、嫌な気持ちになるのではないかと思いきや、ここだと双子同士の友達ができるという理由から人気も高いようです。さらに、国立の中高一貫校であるため、学費の負担が少なく、親にとってもメリットが大きいことから、毎年、多くの双子が受験しているようです。 |
リニアモーターカーは、すでに日本で運用されている現在、リニア中央新幹線は2027年の東京・名古屋間開業に向けて計画が進められています。これが実現すれば、日本で初めて乗客用のリニアモーターカーが走ることになると思っている人がいるかもしれません。しかし、これは間違いで、日本にはすでにリニアモーターカーが運行しています。 たとえば、都営地下鉄大江戸線です。宙に浮いていないため、普通の電車に見えるかもしれませんが、実はれっきとしたリニアモーターカーです。というのも、リニアモーターカーの定義は、円筒型のモーターを使わず、直線型のモーター(リニアモーター)を使って動くものとされているからです。そのため、大江戸線は宙に浮いていなくても、定義上リニアモーターカーに分類されます。大江戸線は床下と線路に電磁石を設置し、リニアモーターを使用して走っています。この形式は他にも大阪メトロの長堀鶴見緑地線や今里筋線、横浜市営地下鉄グリーンラインなどでも採用されています。 また、宙に浮くスタイルのリニアモーターカーは、愛知高速交通東部丘陵線、通称「リニモ」で採用されています。このように、リニアモーターカーはすでに日本各地で走っています。 |
| 掲載日時 | 2025/3/28 18:00 |
|---|---|
| タグ | 聞くトリビア 大橋俊夫 |
クイズに関するニュースやコラムの他、
クイズ「十種競技」を毎日配信しています。
クイズ好きの方はTwitterでフォローをお願いします。
Follow @quizbang_qbik
![[PR]簡単!クイズイベントのお助けツールは、アンサータッチ](https://www.quizbang.net/wordpress/wp-content/uploads/2023/06/c442ab583ef5a93b6e362839cfeb0e34-e1685582257127.jpg)