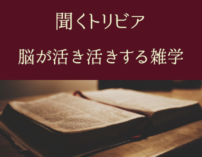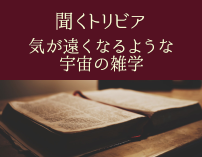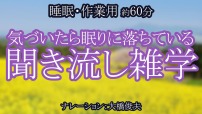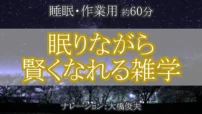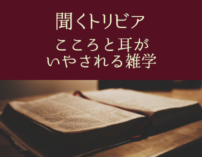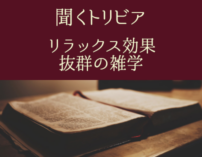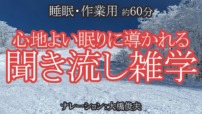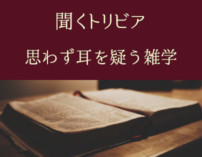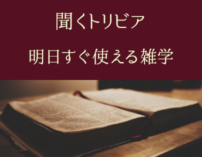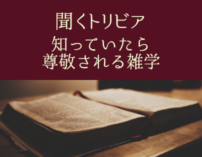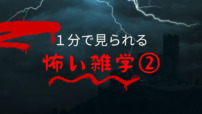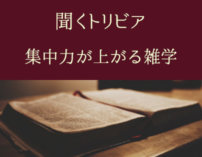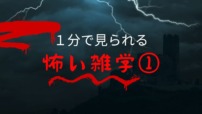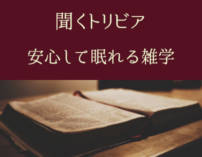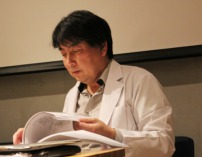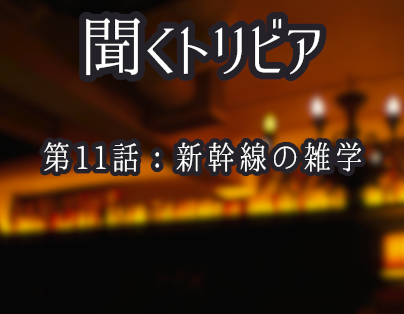『YouTube公開』ペットのネコは30年で○○が2倍になった!
【朗読】ストレスが軽くなる雑学【聞くトリビア】
『ネコも認知症になる!?』
『コアラは体温を下げるために木に抱きつく!?』
聞いているうちに心がスッと軽くなる、面白雑学動画!
驚きの雑学の数々を、フリーアナウンサー大橋俊夫氏の朗読とともにお楽しみください。
こちらは動画の内容の書き起こし記事です。
音声と一緒にお楽しみください。
お土産として売られている「星の砂」は、本当は砂ではない沖縄のお土産としておなじみの「星の砂」。小さなガラス瓶に入れられて販売されています。その名前から、実際に星の形をした砂が存在するものだと思っている人も多いでしょう。しかし、この星の砂、実際には砂ではありません。 では、その正体は何かというと、有孔虫という生物の殻です。この生物はアメーバのように柔らかい体を持っていますが、死ぬとその体は分解され、殻だけが残ります。そして、その殻が星の砂として売られているというわけです。 そんな星の砂は主に炭酸カルシウムで出来ています。実はサンゴ礁の形成にはこの炭酸カルシウムが欠かせません。星の砂は沖縄の美しいサンゴ礁を作るための重要な役割も果たしていたのです。 ちなみに、星の砂を顕微鏡で見てみると、小さな穴が開いています。この穴は有孔虫が足を出すためのもので、その足を使って移動したり、エサを捕ったりするそうです。 |
ハリウッド映画では、子役は双子が採用されやすいアメリカのハリウッド映画には多くの子役が出演していますが、実はアメリカでは、子役として双子が抜擢されることがよくあるそうです。 というのも、ハリウッドでは子役が撮影に参加できる時間が法律で厳しく制限されており、1日あたりの撮影可能時間が決められているからです。そうなると、子役が登場するシーンの撮影がかなり限定されてしまい、制作進行に大きな支障をきたすことになります。そこで、双子を採用して2人1役で出演させることで、1人の撮影時間が終了した後に、もう1人と交代するという形を取って、実質的に撮影時間を2倍にできるというわけです。また、この方法を応用して、何組もの双子を出演させた作品や、三つ子、四つ子をキャスティングした作品もあるそうです。 そのため、ハリウッドのスタッフは、出演可能な双子を探すために奔走しており、映画業界に双子などを紹介する専門の会社も存在するとのこと。こうした仕組みが生まれた背景には、子どもに対する責任を大人が強く問われるアメリカならではの事情があるというわけです。 |
ノルウェーには、椅子の代わりにバランスボールを導入した学校があるよくエクササイズなどで使われるバランスボール。不安定なため、うまく座れない人もいるのではないでしょうか。北欧の国・ノルウェーでは、そんなバランスボールを椅子代わりに使っている学校があるそうです。 これはもともとその学校に関わっている理学療法士が、バランスボールを椅子として取り入れれば、若い頃から生徒たちの体幹や筋肉を鍛えることができるのではないかと考え、発案したそうです。当初は2クラスだけで試験的に導入しましたが、次第に効果があることがわかり、10歳から13歳までの生徒全員の椅子をバランスボールに変えたということです。 また、バランスボールの導入でメリットが生じたのは子どもたちだけではありません。学校側としても、バランスボールは通常の椅子よりも価格が安いため、コスト面で良い効果が生まれたとのこと。 今後、もしかするとノルウェーだけではなく、世界中の学校でバランスボールを使っている風景が見られるかもしれません。 |
イヌの首輪にあるトゲトゲは、単なる飾りじゃないペットとして飼われているブルドッグやドーベルマンなどの凶暴そうなイヌの首輪には、金属のトゲトゲがつけられていることがあります。このトゲトゲ、ただでさえ怖いイメージをさらに強めるためにあるものではないかと思われるかもしれませんが、実は違います。 首輪のトゲトゲ、正確には「スタッズ」という名前で、昔のヨーロッパではすでに首輪につけられていました。当時の犬はペットではなく、猟犬として飼われていることが多く、そのため、猟などでオオカミなど他の動物に狙われやすく、急所である首に噛みつかれて命を落とすこともしばしばあったといいます。そこで首輪にスタッズをつけることで、他の動物から首を守っていたというわけです。 現在は、イヌたちは猟に出ることはほとんどないため、スタッズは当時の名残として、おしゃれなアクセサリーのひとつとして残っています。また、当時に比べて触れてもケガをしないよう、安全性が高いものとなっています。 |
畑で栽培される米もある一般的には田んぼでは米が作られ、畑では野菜や豆などが作られるというイメージが強いかもしれません。しかし、実は畑で作られる稲も存在します。「陸稲(りくとう・おかぼ)」と呼ばれるもので、田んぼで作られる稲に比べて収穫量は少なく、味もそれほど良いわけではないそうですが、畑に直接植えて作るため、労力をかけずに作れることや、病気に強いといった特徴があります。 陸稲は、かつて東北より南の地域で盛んに作られていましたが、水路が発達したことや、品種改良が進んだ結果、田んぼ栽培の稲のほうが多く作られるようになり、あまり見られなくなりました。しかし、現在でも茨城県や栃木県などでは栽培されており、陸稲のほとんどがもち米であるため、あられやおかきといった米菓の原料として利用されているそうです。 この陸稲、プランターで栽培できるため、家庭菜園で栽培している人もいるようです。興味がある方は、自宅でお米作りに挑戦してみてはいかがでしょうか。 |
世界でもっとも古い宿は、日本にある山梨県の南西部に位置する早川町。その深い山に囲まれた、まさに秘境と言っても過言ではない場所に、慶雲館という旅館があります。実はこの宿、創業が慶雲2年、西暦で言うところの705年と、1300年以上の歴史を誇り、2011年には「世界で最も古い歴史を持つ宿」としてギネス世界記録にも認定された、由緒ある旅館なのです。 この慶雲館は、同じ705年に開かれた西山温泉を起源とする宿で、この温泉には疲労回復をはじめとした様々な効果があるとされ、当時から多くの人々が訪れていたそうです。また、徳川家康や武田信玄といった歴史上の人物も湯につかっていて、中でも武田信玄はこの宿を非常に気に入ったらしく、慶雲館に銅鑼を贈ったとされています。この銅鑼は現在でも家宝として慶雲館の当主に受け継がれています。 ちなみに、この慶雲館は近くを流れる川の増水により、昭和に入ってからだけでも4度、建物が流されるなどの水害を受けたことがあり、さらには火災や落石による被害も被ったことがあるそうです。そのたびに、立ち直ったからこそ1300年以上もの歴史を持つようになったといえるのかもしれません。 |
徳島県では、カタカナで「サラダ」と書く地名がある日本には変わった地名が多く存在します。その中のひとつに、徳島県三好市池田町の「サラダ」というものがあります。このサラダ、漢字ではなく、カタカナで「サラダ」と書きます。JR阿波池田駅を含む周辺の地域一帯を指す地名で、駅を出て歩いていると交差点や店の看板に記載されている住所に「サラダ」という表記が見られます。 なぜこのような地名になったのかというと、実は料理の「サラダ」とは一切関係がなく、この地にまるでお皿のような田んぼがあったことから、また、まっさらな田んぼがあったから「さらの田んぼ」が略されて「さらだ」となったと言われています。ただし、江戸時代までは漢字で書かれていたようで、明治に行われた地租改正の際に、わざわざカタカナに変更されたとのこと。なぜカタカナに変更されたのかは定かではありませんが、一説では、時代が明治に変わったので、何か新しいものを取り入れたいという意図があったのではないかと言われています。 ちなみに、この周辺は「サラダ」だけでなく、「ハヤシ」「シマ」「マチ」といったカタカナ表記の地名も多く残っています。こうした独特の地名を探しながら看板を見て回るだけでも、面白い発見があるかもしれません。 |
食材を切ることができない中華包丁がある普通、包丁といえば食材を切るために使います。ところが、中華料理人が使う包丁の中には、食材を切ることができないものがあります。それが「点心包丁」と呼ばれるもので、通常の包丁にあるはずのするどい刃の部分がないのが特徴です。では、なぜそんな包丁があるのでしょうか。 この包丁は、「点心」で食べられる餃子の皮などを作る際に使われます。中華料理では、中の具が透けて見えるほど薄い餃子の皮を使うときがありますが、このような薄い皮は、手で伸ばして作るのは非常に難しいそうです。そこでこの点心包丁を使い、生地に押し当てて伸ばすことで、極めて薄い皮を作ることができるようになっています。 もともと、このような薄い皮は普通の中華包丁で作られていましたが、中華包丁は重くて使いづらい上に、使うたびに刃がまな板を削ってしまう問題がありました。そのため、これらの問題を解決するために、点心包丁が生まれたのだそうです。 |
インド料理店のナンが大きいのは、日本独自の文化インド料理店でカレーを注文すると巨大なナンがついてくることがあります。皿からはみ出すほどのサイズに驚いた人もいるかもしれません。実は、あのような巨大なナンは、本場インドではほとんど見られないもので、日本独特のものだそうです。 なぜ巨大なナンが生まれたかというと、その発端は1990年代にさかのぼります。当時、日本ではインド料理店が次々とオープンしました。その中で、日本人を楽しませるインド料理をどうすれば提供できるかと各店が試行錯誤した中で、ナンを巨大化させて喜んでもらおうという店が登場し、これが成功したため、他の店にも広がる形で大きなナンを提供する店が増えていったとのこと。 先ほど、巨大なナンを出す店はインドにないと述べましたが、そもそもナン自体がインドのレストランではそれほど一般的ではないそうです。ナンは北インドやパキスタンの一部地域で食べられている料理です。多くのインド人はナンを見たことすらないこともよくある話で、中には、日本に来て初めてナンを食べたというインド人もいるようです。インドではナンが当たり前だと思っているのは日本人だけかもしれません。 |
アフリカの国ケニアは、キャッシュレス大国日本でも「PayPay」などのキャッシュレス決済が普及しつつありますが、現金主義の人も依然として多く、現金しか使えない店も少なくなく、「日本はキャッシュレスが浸透している」とは、まだ言い切れない状況です。そんな中、キャッシュレス決済が発達し、成人のうちのおよそ8割が利用しているという国がアフリカにあります。それはケニアです。 ケニアには「M-PESA(エムペサ)」と呼ばれるモバイル決済サービスがあります。2007年にサービスが開始してから急速に若者を中心に広まり、今ではケニア最大の決済サービスとして支持されています。このサービスでは買い物はもちろん、給料の受け取りや公共料金の支払い、家族への送金も行えるため、今やケニアにはなくてはならない存在となっています。 では、なぜケニアがキャッシュレス大国になったのでしょうか。それは、ケニアは治安が悪く、現金を持って出歩くことが大変危険だから。また、日本のように銀行の支店が至る所にあるわけではないため、現金を引き出すことも容易ではありません。こうした背景から、現金を持ち歩かなくてもスマートフォンひとつで簡単に決済ができるモバイル決済が普及したというわけです。 |
エベレストを走るマラソン大会がある世界には100km以上の距離を走ったり、サハラ砂漠を舞台にするなどの過酷なマラソン大会が数多くありますが、そのひとつに、世界最高峰を舞台に開催される「エベレストマラソン」という大会があります。 これは、世界で初めてエベレストの登頂に成功した登山家のヒラリーと、そのガイドを務めたテンジンの偉業を称えるために開催されているもので、世界でもっとも高所で行われるマラソン大会としてギネス世界記録に認定されています。 とはいえ、さすがに山頂を目指すというわけではなく、エベレストのベースキャンプからナムチェバザールという街までを走るものとなっています。それでも、スタート地点のベースキャンプは標高5364mに位置しているため、高所に体が慣れていないと簡単に高山病にかかってしまいます。そのため、参加選手は2週間ほど前から現地入りし、周辺を歩くなどして高地順応のトレーニングをしているそうです。 かなりハードな大会ではありますが、エベレストの麓を走るという貴重な体験ができるため、多くの人の注目を集めています。 |
サンリオピューロランドに出入り禁止をくらったサンリオキャラクターがいる東京都多摩市にある人気のテーマパーク、サンリオピューロランド。ここに行けばすべてのサンリオキャラクターに出会えると思うかもしれませんが、実はかつて、ここを一時的に出入り禁止となったキャラクターが存在します。 そのキャラクターとは、卵をモチーフにしたキャラクター「ぐでたま」です。やる気のない性格が特徴で、過去に食べ物をモチーフにしたキャラクターで行われた「食べキャラ総選挙」で2位に選ばれた際も、「順位とか、どーでもいい」といったやる気のない発言をし、注目を集めていました。 そんなぐでたまは、かつて無許可でパレードに参加したり、入口付近で寝そべってお客さんの通行を妨げる行為を行ったことがあり、それを見かねた“偉い人”が、ぐでたまをピューロランド出入り禁止にしたというわけです。 しかし、この処分を受けて、ぐでたまの相棒である「ニセたまさん」の思いつきで、ピューロランドの外でぐでたまによるイベントが開催され、そこでの頑張りが認められ、最終的にぐでたまの出入り禁止処分は撤回されたということです。 |
コアラがずっと木に抱きついているのは、体温を下げるためコアラと聞いて皆さんが思い浮かべるイメージは、木に抱きついている姿ではないでしょうか。しかし、なぜコアラはいつも木に抱きついているのか、その理由を知っている人は意外に少ないかもしれません。実はこの行為にはちゃんとした理由があるのです。 というのも、コアラは汗をかくことがありません。そのため、体温調整が難しく、体温が上がりやすいという傾向があります。そうなると問題になるのが脱水症状です。そこで、冷たい木の幹に抱きつくことで体を冷やし、体温の上昇を防いでいるというわけです。木の幹は外の気温に比べておよそ9度ほど温度が低いとされています。その冷たさを利用してコアラは自分の身を守っています。 2009年、オーストラリアでは熱波が発生し、多くのコアラが命を落とすという悲劇が起こりました。暑さに弱いコアラにとって、熱波などの厳しい環境を生き抜くためには必死に行動しなければなりません。我々がかわいらしいと思って眺めている木に抱きつく姿も、コアラにとっては生き延びるための必死の行動だったのでした。 |
福岡市では、夜中にごみ収集を行っているゴミ収集といえば通常は朝に行われます。出勤の際にゴミを持って家を出る光景は、どこの家庭でも見られるものではないでしょうか。しかし、福岡市ではちょっと違います。というのも、福岡市ではゴミの収集が夜間に行われているからです。 これは、明治時代に福岡市のゴミ収集が民間の手で行われていたことに由来します。当時、ゴミ収集は市ではなく、農家などの民間人が兼業で行っていました。彼らは自身の仕事に取り掛かる前、すなわち早朝に収集を行っていたため、他の人は朝に間に合うよう、夜のうちにゴミを出す習慣が定着しました。それが受け継がれ、現在の夜間収集へとつながっているというわけです。 また、夜間にゴミを収集することで、朝の通勤時間と重ならず、収集車による交通渋滞を引き起こす心配がないことや、明け方に活動するカラスによる被害を回避できること、夜間にゴミ収集車が巡回することで防犯や防災につながるなどのメリットがあるため、この方式が現在でも続けられているのだそうです。 |
北海道の郵便配達用のバイクには、ヒーターがついているものがある郵便配達の職員は、冬のどんな寒い中でもバイクを走らせて郵便物を運んでくれます。北海道など雪が多い地方では、どんな大雪や吹雪の中でも休まず配達してくれるため、その姿を見ていると、本当に大丈夫なのかと心配になることもあるでしょう。しかし、そこはしっかりと対策が考えられているようで、なんと北海道で使われる郵便配達用のバイクにはヒーターが設置されています。 このヒーターは、バイクのハンドル部分に取り付けられているもので、スイッチを操作することで7段階の温度調整が可能です。さらに、ハンドルにはもちろんフードもついています。 このような機能がつけられている背景には、配達員は郵便物を手に持つ必要があり、厚手の手袋を使うことができないという事情があります。そのため、バイク用ヒーターは北海道での配達には欠かせない必需品となっています。ちなみに、このヒーターを使用すると、手袋が必要ないほど暖かいそうです。 |
バスケットボールのゴールリングの裏にボードがあるのは、観客の邪魔を防ぐためバスケットボールのリングの後ろには「バックボード」という板が必ずつけられています。このボードのおかげで、ボールがリングに入りやすくなる効果もあります。しかし、最初にバックボードが設置されたのは、ボールが入りやすくするためではなく、別の目的があったそうです。 バスケットボールが考案されたのは1891年のこと。その物珍しさから多くの人が観客として試合を見に訪れていました。しかし、当時はまだバスケットボール専用の会場がなく、学校の体育館などで試合が行われていたため、ちゃんとした観客席もありませんでした。そのため、観客がリングのすぐ裏側で観戦することもあったそうです。そして、当時はまだバックボードがなかったため、マナーの悪い観客がゴールを手で妨害することもしばしば起こっていました。これでは試合が成立せず、ついには選手たちからも苦情が寄せられるようになりました。そこで、観客の手が届かないようにするため、バックボードが設置されたというわけです。 当初は仕方なくつけていたバックボードですが、これにより結果的にボードを利用した多彩なシュート技術が生み出され、結果的にバスケットボールの魅力を引き立てる要素のひとつになっていったのです。 |
茶室の入口が狭いのは、武士が刀を持って入れないようにするため茶室で行われるお茶会に参加したことがある人はわかると思いますが、茶室の入口は低く、非常に狭い造りとなっています。この入口は「にじり口」と呼ばれています。このにじり口がこのような大きさになったのは、最初に取り入れた茶人・千利休のある思いが込められているからです。 千利休が生きていた戦国時代は、武将と部下の上下関係が非常に厳しい時代でした。そんな中、千利休は、せめて茶室の中だけでも上下関係を取り払って、すべての人が平等である空間にしたいと考えていました。そこで考案されたのがにじり口でした。入口を低くすることで、どんな身分が高い人でも頭を下げて茶室に入らざるを得ません。茶室の中では誰も威張ることなく、お茶の席を楽しんでほしいという思いが、このにじり口に込められているのです。 また、武士は刀を持ったままではにじり口をくぐることができません。身分を超えて交流を楽しむ場である茶室に刀を持ち込まれると緊張感が生まれてしまいます。そのため、刀を外してから茶室に入ってほしいという思いもあったそうです。 |
日本のゲーム機が、軍事利用されるという理由で輸出規制を受けたことがある2000年、当時人気のソニーのゲーム機「プレイステーション2」が、海外に持ち出す際に許可が必要となる規制対象製品に指定されたことで話題となりました。というのも、プレイステーション2が軍事兵器などに転用される可能性が指摘されたからです。 プレイステーション2のグラフィック処理能力はあまりにも優れたものでした。そのため、この技術がミサイルの軌道計算などに利用できると考えられたためで、その結果、外国為替および外国貿易法の「通常兵器関連汎用品」に指定され、他国に持ち出すには、現在の経済産業大臣にあたる通商産業大臣の許可が必要となりました。 ただし、この規制では輸出申告価格が5万円を超える場合に許可が必要となります。当時、プレイステーション2の価格は3万9800円であったため、1台だけ持ち出す場合には特に問題はありませんでした。とはいえ、ゲーム機が軍事的な理由で輸出規制を受けていたというのは、驚くべき話です。 |
日本の養豚が盛んになったのは、台風がきっかけ現在、日本でも「TOKYO X」や「白金豚(はっきんとん)」など、さまざまなブランド豚が存在し、養豚業も盛んです。そんな日本の養豚業が発展するきっかけとなったのは、かつて日本を襲ったある台風でした。 1959年9月、明治以降最悪とも言われる伊勢湾台風が日本を襲いました。この台風は北海道から四国にかけて甚大な被害をもたらし、死者・行方不明者は5000人を超えました。特に山梨県では被害がひどく、人だけでなく、県内の農畜産業に深刻なダメージを与えました。そんなとき、アメリカ・アイオワ州から台風のお見舞い物資として、生きた豚35頭が山梨県に送られてきました。また、同時にアメリカから養豚技術の指導者も来日し、日本の畜産業を復活させるため、アメリカの最新の養豚技術を山梨県内の農家に指導しました。それにより、山梨県では台風の被害を乗り越え、養豚業も見事に復活したそうです。 その後、この養豚技術は他の都道府県にも広がり、日本中で養豚業が盛んになりました。皮肉ではありますが、台風がなければ、ここまでの養豚業の発展はなかったかもしれません。 |
日本初のマスクの色は、白ではなく黒2019年頃、日本で黒いマスクがブームとなりました。当時、K-POPアーティストが多く使っていたことから、それを真似て多くの若者が着用していました。日本ではマスクといえば白というイメージが強かったため、黒いマスクというものが新鮮でかっこよく見えたのかもしれません。しかし、日本で初めて販売されたマスクは、白ではなく黒だったという驚きの事実があります。 日本にマスクがはじめて登場したのは明治時代初期のことです。当時のマスクは風邪を予防する目的ではなく、炭鉱や工場などで粉塵を吸わないようにするために使われていました。そのため、白いマスクでは粉塵がつくと目立ってしまうことから、汚れが目立たないように黒いマスクが使われていたそうです。 マスクが風邪などに対し衛生的に使われるようになったのは大正時代のことです。当時、世界的にスペイン風邪が流行し、日本でもおよそ38万人もの死者を出すなど大きな被害を受けました。このような状況を受けて、国は国民にマスクの着用を呼びかけました。これにより、マスクは病気を防ぐためにつけるものとして認知が広がることに。さらに、白いマスクが登場したのもこの時期で、ここからマスクは白いものであるというイメージが定着しました。 |
東京タワーを建造した鳶職人は、10円玉を耳に入れていた日本のシンボルである東京タワー。多くの鳶職人が実際にむき出しのタワーに登り、手作業で組み立てをするシーンもありました。そんな彼らの必需品のひとつに「10円玉」があったと聞くとちょっと意外な気がします。彼らは10円玉を耳に入れて作業を行っていたのですが、なぜそんなことをしたのでしょうか。 実は、そうしないと強風で鼓膜が破れてしまうからです。彼らは10円玉を耳栓代わりにしていたのです。高いところでは吹き荒れる風が強く、その音は地上とは比較にもなりません。また、風だけでなく、重機の音も耳を襲ってきます。そこでサイズ的にちょうどよく、コストもかからない10円玉を耳に押し込んで作業したというわけです。 実は、私たちが日常でよく使う耳に入れるタイプのイヤホンは、この職人が10円玉を耳に入れている様子をヒントに生まれたそうです。開発者がこの話を聞いて、だったら10円玉サイズのヘッドフォンを作れば音楽に集中できるのではないかと考え、試行錯誤の末に1982年に誕生しました。 |
イタリアには、ひねるとワインが出る蛇口があるイタリア半島中部、アドリア海に面するアブルッツォ州。ここはワインの産地として知られています。そんなアプルッツォ州にある小さな町・カルダリはユニークなスポットがあり、多くのワインファンが訪れるそうです。そのスポットとは、ひねるとワインが出てくる蛇口です。 この蛇口は、ワイン工場の敷地内にあり、24時間、誰でも利用できるそうです。また代金も必要なく、無料でワインを楽しむことができます。無料ということで、マナーが悪い客が訪れて長居したり、ボトルに移し替えて持ち帰ろうとする人もいそうですが、多くはきちんとマナーを守ってワインを楽しんでいるようです。 なぜ、このような蛇口が誕生したのでしょう。もともとこのカルダリはカトリック教徒が巡礼の際に通る町で、ここで休憩する人もたくさんいました。そんな彼らの喉の渇きを少しでも癒せればということで、ワイン工場が地元のNPO団体と協力して設置したそうです。 ちなみに、平日であればワイン工場も見学できるそうなので、ここを訪れた際には、ただワインを飲むだけではなく、その製造過程を楽しむのも良いかもしれません。 |
ワニの巣の近くにあえて巣を作る鳥がいる獰猛な生物の代表格のワニ。そんなワニの近くになど、誰も近寄りたがらないでしょう。しかし、ワニが生息している場所の近くに、あえて自身の巣を作って暮らしている勇敢な鳥がいます。 その鳥とはアフリカ大陸に暮らすミズベイシチドリで、わずか体長40cmほどしかなく、ワニが大口を開ければ簡単に食べられてしまうほどの大きさです。では、なぜそんな鳥が食べられることを恐れずに巣を作るのかというと、実はワニと協力しあって生活しているからです。 ミズベイシチドリはわざとワニの近くで卵を産みます。そうすることで自分の卵を他の動物から狙われることを防いでいます。そしてその代わりに、ワニがどこかへ行っているときに残ったワニの卵を必死で守ります。そのことをワニが理解しているのか、ワニはミズベイシチドリを襲うことは一切ありません。 お互い持ちつ持たれつの関係で弱肉強食の野生の世界を生きているというわけです。 |
オーストラリアで、酔っ払ったミツバチが発見されたことがあるかつてオーストラリアで、ミツバチが大量死する事件が起こりました。これらのミツバチはしばらく酔っ払うようにふらふらと飛び、最終的には力尽きて墜落し、そのまま死んだそうです。なぜこのような事件が起こったか、実はミツバチたちは、本当に酔っ払ってしまい、急性アルコール中毒で命を落としていたそうです。 では、ミツバチが酔っ払った理由は何か。それはオーストラリアの夏の気温が非常に高かったため、花の蜜が発酵してしまい、それに気づかずにミツバチが摂取したことが原因でした。発酵した蜜を摂取したミツバチは、酔っ払った状態で正常な行動ができず、巣に戻ることができなくなります。また、たとえ戻ることができても、巣を守るミツバチが彼らを締め出すそうです。これは、発酵した蜜を巣に持ち込まれると、これまで集めてきた蜜も発酵してしまう可能性があり、それを防ぐためだそうです。 ちなみに、酔っ払うミツバチは、蜜を積極的に集める真面目な性格のミツバチが多いそうです。必死に働いた結果として巣を追い出されてしまうのは、なんとも気の毒な話です。 |
赤ちゃんは、大人より味覚が敏感大人になれば、子どもの頃に嫌いだった食べ物が食べられるようになったりと、味覚が変わることがあります。大人になると色々な味がわかるようになり、好きな味も広がるからではないかと思いがちですが、実は人生でもっとも味覚を感じるのは、生まれたばかりの赤ちゃんの頃で、その感覚は大人の数倍も敏感だと言われています。 人間の舌の表面には「味蕾」と呼ばれる小さな突起のような器官があります。この味蕾が食べ物の味を感知し、味覚神経を通じて脳に信号を送り、味を判断します。この味蕾、成人男性にはおよそ7千個、高齢男性にはおよそ3千個ありますが、生まれたばかりの赤ちゃんには1万個もあるそうです。味蕾の数がピークを迎えるのは生後3ヶ月頃だそうで、その後、5ヶ月くらいになると味蕾の数はそのままではあるものの、味覚は徐々に鈍くなり、やがて味蕾の数も減少していくというわけです。 子どもの頃に嫌いだったものが大人になってから好きになるのは、実は味蕾の数が減ることで味覚が鈍り、子どもの頃に苦手だった味をそれほど強く感じなくなるためです。つまり、味がわかるようになったからというポジティブな理由ではありません。 |
痛みをまったく感じずに生きてきた女性がいるスコットランドで暮らす女性、ジョー・キャメロンさん。70を過ぎた彼女は、一見すると普通の女性に見えますが、実は痛みをまったく感じないという不思議な体質を持っています。 彼女は40年ほど前に出産しましたが、そのときも麻酔薬を使っていないにも関わらずまったく痛みを感じず、またお尻の関節が悪化したときも、うまく歩けないのが不思議に思えたために病院を訪れたところ、関節がひどく損傷していたことが判明したほどでした。さらに、誤ってストーブに手を置いても熱さは一切感じず、しばらくたってから焦げる匂いでようやく気づくほどだったといいます。 なぜ、彼女がこのような体質になったか、様々な研究者たちが調査した結果、痛みや不安に関連する遺伝子が他の人に比べて活動が鈍いことが判明しました。しかし、この遺伝子が痛みにどう関与しているのかについては、いまだ完全に解明されておらず、キャメロンさんの体質を変えることは現時点で難しいようです。 ただ、今後この研究が進めば、キャメロンさんの体質の解明だけでなく、人類の痛みに関する様々なことが判明し、画期的な痛み止め薬の開発につながる可能性があると期待されています。 |
ペンギンは、仲間のペンギンを海に突き落とす氷の上をよちよちと歩く姿がかわいらしいペンギン。しかし、その愛らしい姿とは裏腹に、実は非常に腹黒い一面を持つ動物としても知られています。 南極で生息するアデリーペンギンは、いつも群れをなして行動していますが、彼らが海に飛び込むとき、何の準備も無しにいきなり飛び込むのではなく、まず互いに体を押し合うそうです。その結果、力負けした1匹が海の中に突き落とされ、その様子を群れ全体で観察するのだそうです。そして、突き落とされたペンギンが無事であることが確認できれば、他のペンギンたちも次々に飛び込んでいきます。 南極にはシロクマやセイウチをはじめ、ペンギンの天敵となる動物が多く生息しています。当然、海の中も同様で、シャチが待ち構え、ペンギンたちを捕食することもあります。仲間が全滅するのを防ぐため、かわいそうではありますが、1匹に生贄になってもらうことで生き延びているのです。野生で生きていくことは、それだけ過酷で厳しい環境に適応しなければならないということなのでしょう。 |
ペットで飼われているネコの平均寿命は、ここ30年で倍以上になった現在、ペットとして飼われているネコの平均寿命は15年から16年ほどだそうです。しかし、今から30年ほど前の1990年代は、ネコの平均寿命は現在よりも10年ほど短く、5歳から6歳程度だったそうです。 というのも、当時のネコはあまり室内で飼われることが少なく、外で生活することが一般的だったためです。その結果、交通事故や猫同士のケンカによるケガや、外で感染した病気により命を落とすことが多くありました。しかし、現在では室内飼育が主流となり、さらに伝染病に対するワクチンも発達したため、大幅に寿命が伸びたとされています。 また、ネコは10歳を超えると慢性腎不全を発症しやすく、これが原因で命を落とすことが多いとされています。しかし、現在ではその治療薬も開発され、腎不全のリスクを減らす成分が含まれたキャットフードも販売されています。こうした進歩により、今後さらにネコの平均寿命が伸びるのではないかとも考えられています。 ただし、寿命が伸びることで新たな問題も生じています。たとえば、ネコにも老化による認知症があるようで、発症すると飼い主にとって大きな課題となることがあります。そのため、飼い主はこうした点を理解したうえでネコを家族として迎えることが大切です。 |
アメリカには誰でもダイヤモンドを採掘できる州立公園があるアメリカ、アーカンソー州のマーフリーズボロという小さな田舎町には、一風変わった公園があります。その名も「ダイヤモンドクレーター州立公園」というもので、その名から想像できるかもしれませんが、この公園ではダイヤモンドが産出されています。しかし、ここの公園のすごいところはそれだけではなく、一般の人でもダイヤモンドを採掘でき、見つけたダイヤモンドを持ち帰ることが許されているという点です。 とはいえ、そんな簡単にダイヤモンドが見つかるわけがないと思われるかもしれませんが、実際には毎日1、2個ほどのダイヤモンドが見つかっているそうで、2015年にはおよそ8.5カラット、グラム換算すると1.7グラムほどのダイヤモンドが発見されたという記録が残っています。このダイヤモンド、日本円で800万円以上の価値があるそうです。 もともと、このマーフリーズポロはダイヤモンド採掘で有名な町で、1906年に初めて原石が発見されて以降、多くの人が訪れるようになりました。現在でも小さな町ながら、年間およそ12万人もの観光客が一攫千金を夢見て訪れています。 |
ザトウクジラは、他の動物を守るためにシャチと戦う世の中には義理人情に厚い人もいたりしますが、それは動物の世界にも当てはまるようで、自分の仲間でもないどんな動物でも襲われていたら助けようとする動物がいます。それがザトウクジラです。 ザトウクジラは、獰猛なシャチに襲われているアザラシやアシカなどを見かけると、彼らを守るためにシャチと戦います。ザトウクジラは鋭い歯などはありませんが、巨大なヒレや尻尾で叩きつけたり、体当たりで突進することでダメージを与えていきます。その攻撃力は非常に強力で、ザトウクジラの巨体による衝撃を受けたシャチはひとたまりもありません。最終的にシャチはあきらめて逃げていくようです。アザラシやアシカにとって、ザトウクジラはまさに命の恩人といえる存在です。 では、なぜザトウクジラはケガをするリスクを負ってまでシャチと戦おうとするのか、実は、その理由ははっきりわかっていません。ただ、幼いザトウクジラの赤ちゃんや子どもがシャチに狙われることが多いため、それを未然に防ごうとしているのではないかとも考えられています。 |
フランスではかつて、学校給食にワインが出されていたワインの本場であるフランスでは、ワインは単なるお酒としてだけではなく、健康に良い効果があり、体を強くする特別な飲み物として考えられていました。そして、その考えは子どもたちの間にも浸透しており、フランスではかつて、学校給食にワインが出されていたという記録が残っています。 1950年代までのフランスでは、子どもたちは学校だけでなく家庭でも毎日ワインを飲んでいました。当時の親たちは、ワインは子どもの成長に欠かせないものだと信じていたからです。中には、学校に行く前にワインを飲ませた結果、子どもが酔っ払ってしまうということもあったそうです。 しかし、さすがにこのような状況は問題ではないかと考える科学者も現れ、次第に子どもにアルコールを与えるのは良くないという考えが一般的になっていきました。そして、1956年には学校給食で14歳以下の子どもにワインを提供することが禁止となり、その代わりに牛乳が出されるようになったそうです。 現在のフランスでは、ワインが飲める年齢は16歳から。ところ変わればルールも様々ですね。 |
スペインには、毛の白いゴリラがいたスペインのバルセロナにあるバルセロナ動物園。ここにはかつて、真っ白な毛を持つ非常に珍しいゴリラが飼育されていました。 そのゴリラは、スペイン語で「小さな雪のひとひら」という意味の「コピート・デ・ニエベ」と呼ばれていました。1966年にアフリカの赤道ギニアで捕獲されてバルセロナ動物園に連れてこられ、2003年に皮膚がんで亡くなるまでおよそ40年にわたり暮らしていました。当時、コピート・デ・ニエベはその珍しさから大人気となり、地元の観光ガイドブックの表紙を飾ったり、非公式ながらバルセロナのマスコットとしても広く知られるようになりました。 なぜこのような色のゴリラが誕生したかについて、研究チームは、家族などの近親交配により遺伝子に異常が起こり、アルビノ(先天性色素欠乏症)となったのではないかと発表しています。 バルセロナ動物園のゴリラ館では、今でも彼に関する写真や展示物があり、当時の様子を知ることができます。 |
パキスタンでは、7割の人が親族同士で結婚している日本では親族同士の結婚はあまり一般的ではありません。いとこ同士の結婚は法律的には可能ですが、実際にはほとんど例を見ないでしょう。一方で、パキスタンでは、結婚した人のおよそ7割が親類同士の結婚であるというデータがあります。 パキスタンでは、文化的にも親類同士の結婚は認められており、むしろ推奨される傾向が見られます。これは、パキスタンにイスラム教徒が多く、イスラム文化の中で近親婚が肯定的に捉えられていることが大きいようです。ちなみに、近年パキスタンからの移民が増加しているイギリスでも、移民コミュニティの中でいとこ同士の結婚が増加しているとされています。 しかし、近親婚は遺伝的リスクが高いとされています。近親婚の夫婦から生まれる子どもは死産が多かったり、生まれてきても遺伝子異常による病気に苦しむ可能性が高いそうです。特に聴覚障害が顕著であり、パキスタンでは毎年生まれてくる子どものうち、およそ2~3%が聴覚障害を持つとされています。そのため、科学者たちは近親婚を避けるべきだと警鐘を鳴らしています。 |
南極には「血の滝」と呼ばれる滝がある南極のマクマードドライバレーと呼ばれる地域には、非常に不気味な滝が存在します。それは「血の滝」と呼ばれるもので、その名の通り血のような赤い水が勢いよく流れています。もちろん、この赤い水は本当の血ではありません。では、なぜこのような赤い水が流れているかというと、この水が非常に多くの鉄分を含んでいるからです。 血の滝は氷河の上に位置しますが、この氷河には「ナノスフェア」と呼ばれる鉄分などを豊富に含む非常に細かい粒子が存在します。血の滝は、氷河が溶けた水が流れることにより形成されていますが、水にはナノスフェアが多く含まれています。このナノスフェアに含まれる鉄分などが地上の酸素や太陽の光などと化学反応を起こすことで、水を赤く染めているということです。 ちなみに、科学者たちが血の滝が赤い原因を解明するのに、1世紀以上もかかっています。南極には他にも我々の想像を超える謎がまだまだたくさん隠されているのかもしれません。 |
ギャンブルで、勝負して負けても、掛け金を2倍にしていけばやがて儲かるという法則がある一攫千金を狙ってギャンブルに手を出す人は少なくありませんが、だいたいの場合、負けてかえって大きな出費をしてしまうのが現実です。そんなギャンブルの世界で「絶対に負けない」といわれている必勝法があるそうです。 その必勝法とは「マーチンゲール法」というもので、「倍賭け法」とも呼ばれます。この方法はどのようなものかというと、競馬や競輪などで、負けた次の勝負で倍のお金を賭けるというものです。たとえば最初の勝負で100円を賭けて負けた場合、次の勝負では倍の200円を賭けます。それでも負けたら次は400円、800円、1600円と、賭けていきます。このようにして1度でも当たればそれまでの損失をすべて取り返し、プラスの収益を得ることができます。しかもこの方法は、オッズが2倍以上あれば成立するので、無理に大穴を狙う必要もありません。 しかし、このマーチンゲール法はあくまで確率論にもとづいた考え方であり、ギャンブル本来の運や偶然性は考慮されていません。また、この方法を成功させるには十分な軍資金が必要となります。すなわち、確実に儲かるわけではありません。もしチャレンジするのであれば、それなりの覚悟はしておいたほうが良いでしょう。 |
初代のリカちゃん人形は、醤油工場で作られていた1967年、現在もヒットを続けるタカラトミーの着せ替え人形、リカちゃん人形が発売されました。当時、このような人形は外国人がモデルだったため、サイズが大きいものばかりで、日本の住宅事情にあまりマッチしませんでした。そこで、日本に合った独自の着せ替え人形ができないかということで開発されたのが初代のリカちゃん人形でした。 そんなリカちゃん人形、デザインも名前も決まり、ついに生産に取りかかれるというタイミングで、人形の工場が他社からの発注でスケジュールが埋まっており、製造ができないピンチに陥りました。このままだと発売日に間に合わない、ということで担当者がどうにかして生産できる工場はないかと探したところ、たどり着いたのはなんと、千葉県にある醤油工場でした。ここがリカちゃん人形の生産を一気に引き受けてくれたことで、無事に間に合い、発売に至ったそうです。 ちなみに、製造の際には近所の主婦が集められ、わずか1ヶ月の間に顔の描き方や髪のセット方法などをマスターしてもらい、なんとか仕上げたとのこと。もし、醤油工場と主婦の力がなければ、リカちゃん人形のヒットはなかったのかもしれません。 |
スペインの国歌には、歌詞がないよくスポーツイベントなどの開会式で国歌斉唱が行われます。最近では有名歌手が参加することも多く、注目を集める場面のひとつでもあります。そんな国歌斉唱ですが、国によってはできないことがあります。というのも国歌に歌詞がない国があるからです。 その国とはスペインです。スペインは、もともと軍隊で使われていた行進曲を国歌として使っています。過去に何度か歌詞をつけようと試みられ、一般公募も行われたことがありましたが、これだというものがなかったため、結局採用されませんでした。2007年にも政府やオリンピック委員会によって歌詞をつける動きもありましたが、これもうまくいかず、結局歌詞がつけられていない状態が続いています。 また、スペインはカタルーニャやバスクなど、言葉や文化が異なる地域を抱える多民族国家であるため、ひとつの言語で歌詞をつけることが非常に難しいという事情もあります。残念ながら、おそらく今後もスペイン国歌に歌詞がつくことはないと思われます。 |
羽田空港から最初に飛び立った飛行機の乗客は、虫だった1931年、羽田空港、現在の東京国際空港がオープンしました。そこから初めて飛び立った飛行機は、中国・大連へ向かう6人乗りのスーパーユニバーサル型旅客機でした。しかし、そこには操縦士、機関士以外には人は乗っておらず、お客はおよそ6000匹ほどのスズムシとマツムシでした。 このスズムシとマツムシは、大連にあった「東京カフェ」に届けるためのものでした。当時、大連には多くの日本人が生活していました。この東京カフェも、そんな日本人が多く訪れる店だったそうです。そしてそのお客さんたちに日本の秋の気分を少しでも味わってもらおうということで、このスズムシとマツムシが送られました。 また、それまで船だと日本から中国まではおよそ4日かかったため、スズムシやマツムシなどを生きたまま運ぶのはなかなか難しかったそうです。しかし、飛行機の登場で、これらの虫たちを早く運ぶことができるようになりました。この空輸はそれだけ時間を短縮できるということをアピールする目的もあったそうです。 |
イギリスでは、60年以上放送している連続ドラマがある日本でドラマといえば、だいたい3ヶ月で終了します。長くても大河ドラマなどが1年間放送する程度です。しかし、イギリスでは、なんと60年以上放送を続けているドラマがあります。 そのドラマとは、1960年に放送が始まった『コロネーション・ストリート』というもので、世界最古のテレビドラマとして、ギネス世界記録にも登録されています。イギリス北西部にある架空の町、ウェザーフィールドを舞台に、そこで暮らす人々の姿を描いた作品で、庶民派ドラマとして現在も高い人気を誇っています。 もちろんキャストは入れ替わり演じられていますが、中には長年同じ人物を演じ続けている人もおり、ウィリアム・ローチという俳優はケン・バーロウという人物を実に50年近く演じ続けています。彼が結婚した回では、後に放送された当時の皇太子チャールズとダイアナ妃の結婚式の中継を超える視聴率を記録したそうです。 2020年には放送1万回を達成しています。今後もこのドラマは、イギリス国民にとってなくてはならない存在として、放送を続けていくことでしょう。 |
ヘビには、耳がない実は、ヘビには耳がありません。そのため、音もほとんど感知できないそうです。空気中に伝わる音のうち、一定の低い音だけを知覚することができ、それ以外はまったく認識できないのです。では、ヘビはそんな状態でどのように生きていけるのでしょうか。 実は、ヘビは舌を使ってさまざまな状況変化を確認しています。ヘビの舌は非常に敏感で、いわゆる機械におけるセンサー的な役割を果たしています。その舌で感知した情報を脳に伝えて、危険を察知しているというわけです。 また、ヘビは地面をくねくね動きながら移動していますが、こうすることで地面を伝わる音の振動を感知しているそうです。伝わってきた振動を、ヘビはアゴの骨を通じて感じ取り、天敵や獲物がどこにいるかを判断して進んでいます。 ちなみに、ヘビは耳だけではなく、目も退化しており、かすかな光しか感じることができません。こんな状態でも生きていけるのは、舌など他の敏感な部分のおかげだというわけです。 |
| 掲載日時 | 2025/3/14 18:00 |
|---|---|
| タグ | 聞くトリビア 大橋俊夫 |
クイズに関するニュースやコラムの他、
クイズ「十種競技」を毎日配信しています。
クイズ好きの方はTwitterでフォローをお願いします。
Follow @quizbang_qbik
![[PR]簡単!クイズイベントのお助けツールは、アンサータッチ](https://www.quizbang.net/wordpress/wp-content/uploads/2023/06/c442ab583ef5a93b6e362839cfeb0e34-e1685582257127.jpg)