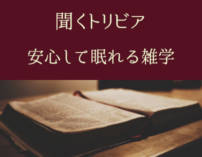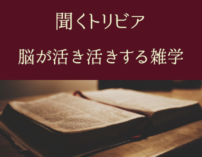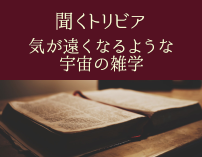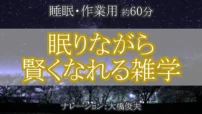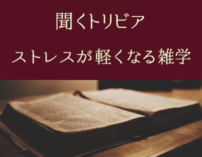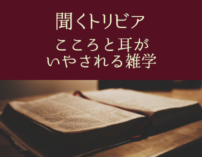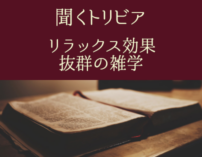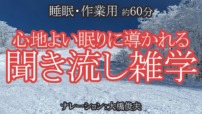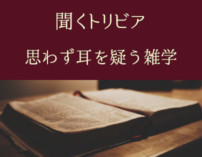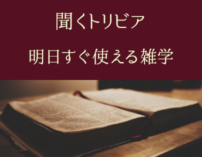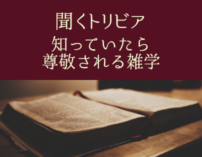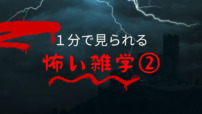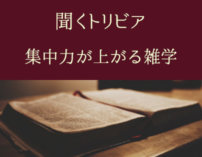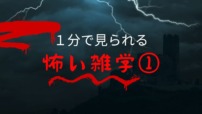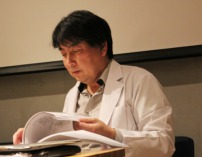名前の由来の雑学
【聞くトリビア 読む編part.10】
ぼんち揚げの名前の由来は山崎豊子の小説。
ぼんち株式会社より発売されている揚げ煎餅「ぼんち揚げ」。(以下、削除)は日本人なら誰しも知る定番おやつのひとつといえるでしょう。
この「ぼんち」の名前は『白い巨塔』などで知られる山崎豊子の「大阪もの」第3作『ぼんち』に由来します。
そのあとがきに「根性がすわり、地に足がついたスケールの大きな《ぼんぼん》 例え放蕩を重ねても、ぴしりと帖尻の合った遊び方をする男が《ぼんち》である」とあり、これにピンときた創業者が、大阪で生まれた揚げ煎餅ということで命名しました。
ちなみに、現在のぼんち揚げのキャラクターはぼんちネコ。大きくなったらライオンになれると夢見ており、その訓練としてぼんち揚げをいつも被っているということです。
ハッピーターンはオイルショックの暗い時代についた名前。
クセになる粉の味などで人気のハッピーターン。
名前を直訳すると「幸せが戻る」となりますが、戻るとは何のことなのでしょうか。
実は亀田製菓がハッピーターンを開発していた頃は第一次オイルショックで日本は非常に不景気でした。
そのため、かつての幸せが戻ってくるようにということで名前がつけられたそうです。
TOPPOの由来。自動車は「トップが高い」、お菓子は「トール+のっぽ」。
「トッポ」と聞くと、車好きなら三菱自動車の車、お菓子好きならロッテのお菓子をイメージすると思います。
同じ名前の全く方向性の違う商品ですが、名前の由来もそれぞれです。
車のほうは、ルーフ、つまりトップが高いことを少し崩してつけられました。
一方、お菓子のほうは「背が高い」を意味するトールと、日本語で同じ意味の「のっぽ」を合わせたものだといいます。
どちらも愛嬌を込めたネーミングといえるでしょう。
麦芽飲料のミロのもとになったレスリング選手はオリンピックで6連覇した。
牛乳に溶かして飲むミロは、子どもの頃一度くらいは飲んだことがあるものでしょう。
このミロの名前の由来は、今から約2600年前のローマのレスリング選手・ミロンに由来します。
当のミロンの実績は、古代オリンピックのレスリングで6連覇という、吉田沙保里や伊調馨以上の超人レベルのものでした。
このミロンにあやかって「強い子どもに育って欲しい」という願いからつけられた名前がミロなのです。
パピコ、ポッキー、プッチンプリン。グリコのお菓子の名前は「パ行」が多い。
グリコに伝わるジンクスがあります。それは「パ行で始まる商品はヒットする」というものです。
タイトルで紹介したものの他にも、プリッツ、パナップなど高い人気を誇るグリコ商品が存在します。
なお、その中のひとつ・パピコの発売当初の1974年、お菓子業界には「白色の氷菓子は売れない」というジンクスもありました。
しかし、味の改良などでこれに勝負を仕掛け、現在は年間売上げ100億円を超えるヒット商品に仕上げています。
クマのぬいぐるみテディベアの「テディ」さんはアメリカ大統領。
テディの愛称で知られたアメリカ大統領は、日露戦争の講和を仲介したセオドア・ルーズベルトです。
大統領になる前から、彼は元々狩猟家や探検家としてネームバリューがありました。
ある日狩りに出かけたセオドア・ルーズベルトは、瀕死の褐色の子熊を見かけましたが、「これを討つのはスポーツマン精神に外れている」と見逃してあげました。
そのエピソードはワシントン・ポストに紹介され、ある菓子店がこれを称えてクマのぬいぐるみを作りました。
これがテディベアのはじまりとされています。
ベーゴマの「べー」は貝の名前から。
ベーゴマのルーツは平安時代の京都まで遡ります。
当時はバイ(海螺)貝という貝に砂や粘土をつめて、紐を使って回したといいます。
現在も関西ではそれに由来する「バイゴマ」の名称が一般的ですが、関東では「ベーゴマ」です。
これは、関東に伝わった際、バイゴマがベーゴマになまったものといわれます。
鉄製のベーゴマが作られるようになったのは明治末期から大正時代にかけて。
戦時中は金属が不足したため、瀬戸物やガラスで代替品が作られました。
韓国の英語名「コリア」は、かつての王朝「高麗」に由来する。
高麗は918年に王建が建てた王朝で、936年に朝鮮半島を統一しています。
高麗は韓国語で「コリョ」と発音し、これがなまって「コリア」になったとされています。
日本の「ジャパン」も、マルコ・ポーロがヨーロッパに紹介したことで知られる「ジパング」が由来とされます。
ちなみに中国を意味する「チャイナ」は始皇帝の秦や、春秋時代の晋が由来など、複数の説があります。
カエデは、葉っぱの形がカエルの手に似ているから。
カエデは漢字では「楓(きへんに風)」と書きましたが、かつては「蛙手(かえるに手)」とも書きました。
実際に「かえるで」と読んでおり、これが変化してカエデになったといいます。
東京の有楽町の名前の由来は織田信長の弟。
信長の弟、織田有楽斎(うらくさい)は織田長益(ながます)ともいい、千利休の弟子でもあった文化人です。
本能寺の変の後は豊臣秀吉に仕え、関ヶ原の戦いでは東軍につきました。
大坂冬の陣の後は隠居して茶の湯に専念した有楽斎。
彼が江戸に構えた屋敷は今の有楽町にあり、その名前は有楽斎から来ています。
また、数寄屋橋の名前も、彼が構えた茶室、つまり数寄屋にちなんだものです。
| 掲載日時 | 2021/2/12 18:00 |
|---|
クイズに関するニュースやコラムの他、
クイズ「十種競技」を毎日配信しています。
クイズ好きの方はTwitterでフォローをお願いします。
Follow @quizbang_qbik
![[PR]簡単!クイズイベントのお助けツールは、アンサータッチ](https://www.quizbang.net/wordpress/wp-content/uploads/2023/06/c442ab583ef5a93b6e362839cfeb0e34-e1685582257127.jpg)