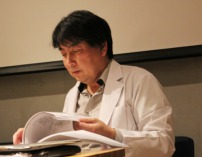モミジDr.のリカバリー日記
第286回「ビタミン」
先日、ふと疑問に思うことがあった。
「ビタミン」はなぜ、「ヴィタミン」と書かないのか?
最近、「bi」を「ビ」、「vi」を「ヴィ」と表記する文化が浸透してきているように思う。
元々、僕が小学生の頃は「ヴィ」と表記することは少なかった。
「デヴィ夫人」がテレビに登場するころからなんとなく、この表記にこだわることが増えてきたように感じる。(あくまでも個人的な考え)
そこで、調べてみると、以下のような歴史をたどっていた。
・1860年、「v」音を表すのに、「ヴ」を用いるのは、福沢諭吉の発案による。『増訂華英通語』に用例が見える
・1954年3月15日 国語審議会「外来語表記について」
「カタカナの使用において、原音における「ファ」「フィ」「フェ」「フォ」「ヴァ」「ヴィ」「ヴ」「ヴェ」「ヴォ」はなるべく、「ハ」「ヒ」「ヘ」「ホ」「バ」「ビ」「ブ」「ベ」「ボ」と書く。」
と指示されている
・1991年6月28日、海部俊樹内閣総理大臣の内閣告示第2号において「外来語の表示」を告示している。
「外来語や外国の地名・人名を原音や原つづりになるべく近く書き表そうとする場合に用いる仮名)に「ヴァ・ヴィ・ヴ・ヴェ・ヴォ」あり。p244「ヴァ」「ヴィ」「ヴ」「ヴェ」「ヴォ」は外来音ヴァ、ヴィ、ヴ、ヴェ、ヴォに対応する仮名である。(中略)注、一般的には「バ」「ビ」「ブ」「べ」「ボ」と書くことができる」、とある。
世の中の流れに伴って、言葉・表記も変わるのだなぁと感心していたのだが、
では、なぜ、「ビタミン」は「vitamin」なのに「ヴィタミン」と書かないのだろう?この整合性の無さは気になるところ。
分かる方がいたら、教えてほしい。
ということで、今年、最後のテーマクイズは「ビタミン」。
(年末年始となる12月29日、1月04日はコラムはお休みで、1月11日が最初となります。今年1年ありがとうございました。来年もよろしくお願いいたします。)
【今週のテーマ「ビタミン」】
科学・グルメの分野から「ビタミン」
問題01
ビタミンやミネラルを豊富に含み栄養価の高いことから「海のミルク」と呼ばれる海産物は何?
問題02
江戸時代には「江戸わずらい」と呼ばれた、ビタミンB1の不足によってかかる病気は何?
問題03
正式には「カルシフェロール」といい、紫外線に当たると生成されるビタミンは?
問題04
ビタミンAに対する「カロチン」、ビタミンDに対する「エルゴステリン」のように、体内でビタミンに変化する物質を総称して何という?
問題05
(四択)次の中で、水に溶けるビタミンは?
① ビタミンA ② ビタミンC ③ ビタミンD ④ ビタミンE
問題06
(四択)次のうち、鈴木梅太郎博士が発見した「オリザニン」の正体は?
①ビタミンB1 ② ビタミンB2 ③ ビタミンB6 ④ ビタミンB12
問題07
(四択)次のうち、作家・重松清の作品は?
①『ビタミンF』②『ビタミンG』③『ビタミンH』④『ビタミンI』
問題08
(四択)次のうち、「重要な生命活動を司るアミン」という意味から「ビタミン」を命名した人物は?
①エイクマン ② フンク ③ セント=ジェルジ ④ ポーリング
問題09
(四択)明治期の海軍軍医総監で、「ビタミンの父」と呼ばれたのは?
① 松本良順 ② 森林太郎 ③ 高木兼寛 ④ 菊池常三郎
問題10
1797年に起きた「スピットヘッドとノアの反乱」で、海軍水兵たちが上官に要求し、反乱の一因となった飲食物は?
①ビスケット ② チョコレート ③ ミルク ④ レモンジュース
正解【ビタミン】
問題01
牡蠣
(カキ、イタボガキ科とベッコウガキ科に属する二枚貝。)
問題02
脚気
(かっけ、英語では「ベリベリ」という。ビタミンB1は「チアミン」。「脚気」は、「多発性神経炎、浮腫、心不全」を三徴とする。)
問題03
ビタミンD
(ビタミンD2は「エルゴカルシフェロール」、ビタミンD3は「コレカルシフェロール」という。不足すると、「くる病」「骨軟化症」「骨粗しょう症」となる。)
問題04
プロビタミン
(その他、ビタミンB5(パントテン酸)に対する「パンテノール」など。)
問題05
② ビタミンC
(ビタミンA、D、E、Kは脂溶性ビタミン、B、Cは水溶性ビタミン)
問題06
① ビタミンB1
(鈴木梅太郎は、長岡半太郎、本多光太郎とともに「理研の三太郎」と呼ばれる。「オリザニン」はラテン語で「稲」という意味。ビタミンB群をまとめると、ビタミンB1は「チアミン」、B2は「リボフラビン」、B3は「ナイアシン」、かつてのB5は「パントテン酸」、B6は「ピリドキシン」、かつて「ビタミンH」でB7は「ビオチン」、B9またはビタミンMは「葉酸」、B12は「シアノコバラミン」)
問題07
『ビタミンF』
(2000年の第124回直木賞受賞作。短編集『ゲンコツ』『はずれくじ』『パンドラ』『セッちゃん』『なぎさホテルにて』『かさぶたまぶた』『母帰る』)
問題08
②(カシミル・)フンク
(ポーランドの生化学者、エイクマンはビタミン発見への貢献から1929年ノーベル医学生理学賞をホプキンスとともに受賞。セント=ジェルジはビタミンCの発見により1937年ノーベル医学生理学賞を受賞。ライナス・ポーリング博士はノーベル賞を化学賞と平和賞で二度受賞したことで知られる。「ビタミンCを摂れば、風邪が治る」を世界的に広めた人物でもある。)
問題09
③ 高木兼寛
(たかぎかねひろ、松本良順は陸軍軍医初代総監で、大磯の日本初の海水浴場を作った人物、森林太郎は文豪・森鴎外のこと、菊池常三郎は、西宮回生病院初代院長。)
問題10
④ レモンジュース
(マゼランの航海で多くの乗組員が「壊血病」で死んでいる。イギリスの海軍軍医ジェームズ・リンドは下級兵士に多くの死亡者が出ていることから栄養状態の差によっておこる病気と考え、乗組員には「柑橘類」の摂取が必要と考えた。しかし、これらの発見は長い間、黙殺されていた。水兵の賃金の安さに加え、衛生管理の上で柑橘類の摂取を要求したことから反乱が起きた。)
| ジャンル | モミジDr.のリカバリー日記 |
|---|---|
| 掲載日時 | 2023/12/21 16:00 |
| タグ | ビタミン |
クイズに関するニュースやコラムの他、
クイズ「十種競技」を毎日配信しています。
クイズ好きの方はTwitterでフォローをお願いします。
Follow @quizbang_qbik
![[PR]簡単!クイズイベントのお助けツールは、アンサータッチ](https://www.quizbang.net/wordpress/wp-content/uploads/2023/06/c442ab583ef5a93b6e362839cfeb0e34-e1685582257127.jpg)