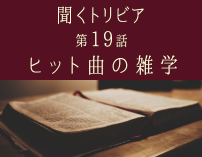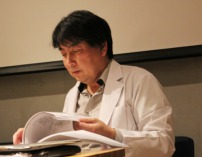自宅でも職場や学校でもない居心地の良い「第三の場所」とは?
コロナ禍に入って約3年。第9波に入ったという話もありますが、初期に比べるとオフラインで人に会う機会は戻りつつあります。人と会えない世の中から少しずつ会える世の中になり、改めてリアルで会う大切さに気づいた人も多いのではないでしょうか。
では、 “オフラインの大切さ” という切り口でこんな話題を。
問題!
日本語では「第三の場所」と言い表すこともある、自宅でも職場や学校でもない居心地の良い場所のことを指す言葉は何?

それは・・・「サードプレイス」です!
自宅をファーストプレイス、職場や学校をセカンドプレイスと言った時、サードプレイスという考え方があります。ファーストプレイスはプライベートな空間、セカンドプレイスは生活していくのに欠かせない場所、そしてサードプレイスは居心地が良くて他者と交流できる場といったところでしょうか。
ところでこの「サードプレイス」という言葉は、アメリカの社会学者レイ・オルデンバーグ氏が、著書『The Great Good Place』(1989年)の中で提唱したもの。アメリカでは車社会が一般的になり、人々が交流する機会が少なくなっていました。そこでレイ・オルデンバーグ氏は、ヨーロッパでパブやカフェが人々の交流の場として重要な役割を果たしていることに着目。
「すべての人に平等」「フレンドリーさがある」「アクセスしやすい」「安心感がある」「会話が重視される」「リラックスできる」などの特徴を持つ場所がサードプレイスとして機能するとしました。
つまり、サードプレイスはここ!と決まった場所を指すのではなく、人によって違うということ。ある人は行きつけのカフェや喫茶店、ある人は地域の井戸端会議、ある人はボランティア活動といったように…。また、サードプレイスにする意味を含めて場所ができることもあります。例えば、コワーキングスペースやコミュニティスペースといった場所です。
こうしたサードプレイスが居場所となるには、いわゆる “ナナメの関係” と言われる人との関係が重要だとよく言われます。親や教師、上司・部下との関係をタテの関係、同僚や友達を横の関係としたとき、そのどちらにも属さない人がナナメの関係です。
サードプレイスは、「〜〜すべき」「〜〜しなければならない」などの縛りを感じることなく、その時その時の心の状態に従って話し、過ごす場所。誰もがより生きやすい社会になっていくためには、今後もっと必要になるのではないでしょうか。
| ジャンル | 生活 |
|---|---|
| 掲載日時 | 2023/9/15 16:00 |
クイズに関するニュースやコラムの他、
クイズ「十種競技」を毎日配信しています。
クイズ好きの方はTwitterでフォローをお願いします。
Follow @quizbang_qbik
![[PR]簡単!クイズイベントのお助けツールは、アンサータッチ](https://www.quizbang.net/wordpress/wp-content/uploads/2023/06/c442ab583ef5a93b6e362839cfeb0e34-e1685582257127.jpg)